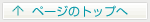寂滅為楽:それでも僕らは研究が好きなんだ
Tweet第1回(更新日:2021年5月30日)
市瀬 智
「契約を更新することができなかった」
33歳になったばかりの12月、小さなキッチンスペースでの夕食を終えたあと市瀬智(仮名)は妻にそう伝えた。大きくなったお腹をさすりながら「そう・・・」とだけ妻は返事をし、そのままキッチンで食器を洗いはじめた。
***
市瀬は某私立大学の薬学部の出身だ。大学に入ったころは周囲の多くの学生と同じように、将来は薬剤師になろうと考えていた。いずれは自分のお店(薬局)も持てればいいなと思っていたとも言う。
その道を”外れた”のは、薬学研究実習として研究室に配属されたことがきっかけだった。多くの学生は卒業に必要な単位が欲しいだけで、配属先の研究室での実験は適当に流すことが普通だったと市瀬は言う。だが市瀬は、自分の実験から新しい事実が見つけられるということに興奮を覚え、どんどんと実験にのめり込んでいった。
持ち前の頑張りと生来の器用さも相まって、市瀬は単なる実習としての実験を遥かに超えた”実験結果”を得ることができた。そして、そこの配属先の教授のすすめもあり、大学院博士後期課程で旧帝大の大学院へと進学することになった。
***
大学院博士課程で在籍した研究室は、その研究分野では日本では5本の指に入ると言えるくらいの有名研究室だった。その名声は広く海外にも知られ、国内のみならず、大学院から入学してくる学生が国外からも毎年何人もいた。そのためか、市瀬は大学院博士後期課程で自身を”外様”と感じることはほとんどなかったようだ。
また、そこの教授・准教授は、数年で形になる研究プロジェクトを学外から来た学生に行わせて論文にする技術・経験に長けていた。その結果、市瀬はこれといった問題もなく無事に博士号の学位を取得し、そのままそこで研究員として2年間を過ごした。そして、そこでの指導教官の強力な推薦状と某財団からの奨学金を持って市瀬はアメリカへの研究留学をする。
奨学金の期間は1年だった。だが、留学先のボスがNIHのグラントを獲得できたということで、奨学金の期間が終えたあとも引き続きポスドクとして研究留学を継続した。
***
市瀬が結婚をしたのは、彼が博士号の学位を取得したタイミングだった。妻は市瀬の出身大学である某私立大学薬学部の2つ下の後輩で、結婚したときは病院薬剤師として働いていた。
市瀬が奨学金を獲得して留学できることになったとき、妻はあまり喜んではくれなかったらしい。実は、市瀬が旧帝大の大学院に進学することについても前向きには捉えていなかったようだ。市瀬がそのことを知ったのはつい最近のことだったようだが。
とはいえ、市瀬の妻にも、市瀬の”挑戦”を応援したいという気持ちはあったようだ。だが、その一方で、研究の世界はそんなに甘いものではないのではないかという疑念も常に持っていたようだ。そのためか、市瀬が留学するときは一緒には渡米せず、別居生活という形を取って病院薬剤師を続けていた。
市瀬の妻は、奨学金の期間が終わったら市瀬は帰国するものと思っていた。そのため、彼が1年間を過ぎても帰国せずに留学を続けると知ったとき、彼女はとても驚いたらしい。そして、市瀬の強い勧めと粘り強い説得があり、彼女は市瀬の留学2年目には日本での仕事を辞めてアメリカで同居することになった。
***
市瀬は妻と同居を始めても、基本的には研究を最優先とした生活を送っていた。だが、アメリカはプライベートの時間を大切にする。新婚旅行もまともにしなかった市瀬夫婦にとっては、アメリカでの生活は毎日が新婚旅行のような感じだったようだ。市瀬はこの頃が人生で一番楽しかったと振り返っている。
アメリカで妻と同居して1年半、待望のベイビーも授かり、市瀬の研究者人生も順風満帆かと思われた矢先に冒頭の出来事が起きた。
そのときの様子を市瀬の奥様に尋ねると、「あの頃は幸せだったけど、自分たちの人生がこのまま上手くいくはずがないとずっと思っていた。だから、そのときに向けての準備はしていたし、あのときは自分より夫の方がショックが大きかったから自分が何とかしないといけないと思っていた。」と答えてくれた。事実、そのときの市瀬の落ち込みようは酷かったらしい。家庭での会話もいつもうわの空で要領を得ず、市瀬の妻は初めての出産をアメリカでほぼ独力で乗り切ったらしい。
***
市瀬の契約が切られたのは何故だったのか。本当のことは留学先のボスにしかわからないが、市瀬によると、彼の留学先での実験そのものには大きな問題はなかったらしい。そのため、彼の契約が切られたのは単に市瀬の給料をカバーしていたNIHのグラントの期間が2年間だっただけ、と市瀬は説明した。事実、契約を更改できないとボスが伝えてきたときの理由がそれだったらしい。
市瀬の契約期間は、当初は翌年の3月までだったが、妻が2月に出産したということを考慮してもらい、5月まで延長してもらえた。それでも結局、契約が切れるまでに次のポスドク先をアメリカで見つけることができなかった。しかも、その時点では、留学中に行っていた研究プロジェクトは論文になっておらず、市瀬は日本でも研究職を見つけることができなかった。
結局、妻のツテで薬剤師の職を日本で見つけ、6月に帰国してからは市瀬は研究職を”廃業”して薬剤師として生計を立てることになった。
***
市瀬は言う。「良い夢を見させてもらえました。後悔が全くないとは言えないですが、アメリカで研究ができたということは、僕の人生には大きな意味がありました。願わくば、息子には僕が叶えられなかった研究者の道を進んでもらいたいなと思っています。」
執筆者:樋口恭介(サイエンス・ライター)
2014年よりサイエンス・ライターとして活動開始。大好評を博した『連載記事:報われないロスジェネ研究者たち』では、世間に見捨てられたロスジェネ世代のバイオ系研究者の真の姿を赤裸々に綴った。編著に研究者の頭の中: 研究者は普段どんなことを考えているのかがある。