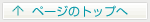SFミステリー小説:永遠の秘密
TweetSFミステリー小説:永遠の秘密
第三章:仲間(2)
田中洋一の予想どおり、羽加瀬信太は、酒見正・一ノ瀬さとしと一緒に渡り廊下の辺りの人気のない場所にいた。
その場所に田中洋一たちが着いたとき、酒見正と一ノ瀬さとしは、少し大きな声で羽加瀬信太に一方的に何かを話していた。それに対し、羽加瀬信太は下を向いたまま何も言い返していなかった。
その様子を見た真中しずえは、「あんたたち何してるの?」といきなり大きな声を出し、ずかずかと酒見正と一ノ瀬さとしに向かって歩いていった。
そんな真中しずえの様子を、田中洋一はオロオロしながら眺めていたが、沢木キョウは表情をほとんど変えずに、真中しずえから少し距離を置きながらも、その後をついていった。
「なんだ、またお前か」と、真中しずえが近付いてきたことに気がついた一ノ瀬さとしが、うっとうしそうに言うと、酒見正は「なんだよ学級委員長、なんか用か?ここは教室じゃないぞ。俺たちは昼休みで遊んでるんだ。邪魔すんな。あっちいけ」と、とても不機嫌そうに続けた。
「何が遊んでる、よ。全然遊んでるようには見えないわ。羽加瀬君をまた困らせてるの?」
「また、ってどういう意味だよ。」
「あなたたちの悪事は知ってるんですからね。」
「悪事?」
「悪いことをしたってことよ。」
「悪事の意味くらいは知ってるよ。バカにすんな。」
「あら、そうだったの?難しい言葉を知ってるのね。」
真中しずえが酒見正をからかって『フフッ』と笑うと、一ノ瀬さとしが怒った表情で真中しずえの前に進んできた。
「おい、あんまり調子に乗んなよ。」
「調子に乗ってるのはどっち?あんたたちが調子に乗って羽加瀬君に無理難題を言って困らせてるんでしょ。」
「誰が困ってるんだって?羽加瀬は俺たちと遊びたいって言うから一緒に遊んでるだけだ。」
「よくそんなウソが言えるね。」
「ウソじゃねーよ。おい、羽加瀬、お前からもきちんと説明してくれよ。この勘違い学級委員長が俺たちに言いがかりをつけてきて困ってるんだよ。」
羽加瀬信太は下を向いたまま何も言わない。
「おい、羽加瀬、聞いているのか?」と、今度は酒見正が羽加瀬信太の左肩を右の掌で押しながら言った。
「暴力はやめなさいよ」と真中しずえが言うと、「これが暴力?ちょっとじゃれてるだけだろ。笑わせんな。本当の暴力がどんなのか知ってるのか?」と、真中しずえの前にいた一ノ瀬さとしが、右手の拳を見せつけるようにしてニヤニヤと笑いながら言ってきた。
「おい学級委員長、気をつけな。一ノ瀬君は空手の茶色帯だぞ。小学校を卒業するまでに黒帯になれそうなくらい強いんだからな」と、こちらもニヤニヤしながら酒見正が続けて言った。
「ふん、なによ、女子にも暴力をふるうっていうの?カッコ悪いわね。空手だか何だか知らないけど、自分より体が小さかったり力の弱い女の子に向けてしか攻撃できないんじゃ、単なる弱いものいじめの意気地なし野郎じゃない。何が茶色帯よ、笑っちゃうわ。」
一ノ瀬さとしをにらみながら強い口調で言い返している真中しずえを、田中洋一は相変わらずオロオロしながら眺めているだけだったが、田中洋一はふと真中しずえの手が震えているのに気がついた。
その様子を見て田中洋一は何か行動を起こさなきゃと思ったが、その瞬間、一ノ瀬さとしが右手を上に上げて真中しずえに殴りかかった。
田中洋一は「あっ」と声を出し真中しずえから視線を外し、真中しずえは少し肩をこわばらせて目をつむった。田中洋一も真中しずえも、その次に何が起こるかを理解し覚悟した。
しかし、予想していた出来事は起こらず、沈黙が続いた。田中洋一は真中しずえの方に恐る恐る視線を戻し、真中しずえは目を開けて、二人がほぼ同時に同じ光景を見た。
一ノ瀬さとしの右のパンチを、沢木キョウが左手でブロックしていた。
「てめえ、何すんだ」と凄む一ノ瀬さとしの方を見ながらも、沢木キョウは「少し離れてた方がいいよ」と表情を変えないまま真中しずえに言った。
「おい、俺の話を無視すんな。」
「女性に手をあげるのはよくないと思うよ。」
「じゃあ、お前にだったらいいんだな。手加減しねーぞ。」
「やめた方がいいと思うよ。」
「もう遅い。お前が入ってきたんだからな。お前が喧嘩を売ったんだぞ!」
「いや、それは違うと思うんだけど。」
「どっちでもいいだろ。後悔すんなよ。」
「後悔するのは君だと思うよ。」
「ふざけるな!」と怒鳴りながら、一ノ瀬さとしが再び右手でパンチを出そうとした瞬間、沢木キョウは一ノ瀬さとしに向かって一歩踏み出し、すばやく右手の手刀を首めがけて突き出した。
その手刀は一ノ瀬さとしに当たるギリギリのところで止まった。意表をつかれた一ノ瀬さとしが驚きの表情で沢木キョウの手刀を見ると、沢木キョウは何事もなかったかのような表情でその手刀をおさめて一歩さがった。
その状況にさらに一ノ瀬さとしは怒り、今度は右足で沢木キョウの左脇腹を蹴ろうとした。しかし、沢木キョウは全く表情を変えないまま、平然と左腕でその蹴りをブロックし、ブロックしたと思った途端に体を左方向に九十度回転させ、右足で一ノ瀬さとしの顔に蹴りを入れる体勢をとった。
一ノ瀬さとしの身長は沢木キョウよりも10cmくらい高かったが、そんな身長差があるにもかかわらず、沢木キョウの右足の靴の裏は一ノ瀬さとしの顎まで軽く届いていた。しかし、今回も沢木キョウはギリギリのところで動きを止めていた。
「これ以上やっても無駄だよ。もうやめよ。」と沢木キョウが言うと、怒りで言葉が出ない一ノ瀬さとしに変わって、酒見正が「おまえ、いったい何なんだよ」と急にオドオドした表情になって聞いてきた。
「別に何でもないよ。僕もアメリカにいるときに空手をやってたんだよね」と、一ノ瀬さとしの顎のところまで上げていた右足を地面におろしながら沢木キョウは言うと、「空手は日本の武術だぞ。アメリカにあるわけないだろ。ウソつくな」と、一ノ瀬さとしは言い返した。その表情はまだ怒ってはいたが、もう沢木キョウに攻撃をしかける様子はなさそうだった。
「うん、たしかに空手は日本で生まれた武術だよ。具体的には沖縄発祥のようなんだけどね。でも、第二次世界大戦の頃に何人かの空手家がアメリカで空手を教え始めたんだよね。で、そのあとで空手はアメリカ全土に広がったんだ。とは言っても、日本の空手とアメリカの空手は型が少し違うんだけどね。」
「お前、帯の色は何色なんだ?」
「帯の色も日本とアメリカでは違うし、アメリカの中でも流派によっては違うんだけど、どこも最初は白で、黒が最終ゴールだよね。もちろん、黒帯をとってからも二段、三段と上はあるけど。で、僕はね、ブラックベルトのSecond Degree、日本でいうと黒帯二段まで進んだんだ。三段のテストを受けようと思ってたけど、急に日本に引っ越すことが決まったから受けられなかったんだ。」
「く、黒帯・・・の二段?」と、さっきよりもさらに元気のない声で酒見正が言った。
「僕はたまたま運が良かったから、みんなより少し早くブラックベルトまでいけたけど、頑張り続ければみんなもいずれは黒帯までいけるよ。一ノ瀬君もあと少しなんでしょ。でもね、僕の師範が毎回のレッスンで何度も言ってことなんだけど、ブラックベルトには型とか技とかだけじゃなくて清く正しい精神も必要なんだよ。空手は、自分より弱いものを脅して自分の言いなりにするための道具じゃない。」
沢木キョウは最後は少し強い口調でそう言ったが、一ノ瀬さとしは「うるせえ!」と、また攻撃的な口調でが拳を振り上げながら大きな声を出した。
「What you learn should be used to defend yourself and your fellow students, and should never be used to attack others or to do bad things in an abusable way」
沢木キョウが急に英語を話し出したので、一ノ瀬さとしは面食らった表情になり、「な、な、なんだよ急に。に、日本語をしゃべれよ・・・い、意味がわかんねーぞ」と少しどもりながら言葉を絞り出した。
「空手の教室で習ったことは自分や仲間を守るために使うべきで、決して他人をいたずらに攻撃したり悪いことに使ってはならない、って意味ね。沢木君が通ってた空手の教室にあった『守るべきルール』と言ったところかしら?」と、空木カンナが突然会話に入ってきた。
その状況にはさすがの沢木キョウも少し驚いたらしく、空木カンナの声がする方を向いて、「空木さん、いつの間にかにいたんだね」と、少し苦笑いをするような表情になりながら声をかけた。
空木カンナは上履きのままで、その隣には保健室の先生である立花美香(たちばな・みか)が立っていた。
「みんなの様子が心配になっちゃったから、立花先生を連れてきちゃった。で、状況を説明したら、立花先生が職員専用の出入り口から外に出てもいいと言ってくれたから近道してきたの。だから、上履きのままなんだけどね」と空木カンナはみんなの方を向いて言うと、立花美香が「校舎に戻るときも私と一緒に来ればいいわ。保健室にあるペーパータオルを持ってきてあげるから、それで靴の底をきれいにしてから校舎に入ってね」とにこやかな上品な笑顔で空木カンナに優しく話しかけた。
そして次に、立花美香は一ノ瀬さとしたちの方を向いて「暴力はいけませんよ。みんな同じクラスのお友達でしょ。仲良くしましょうね」と笑顔を浮かべたまま優しい口調でそう諭した。
しかし、田中洋一には、その目には冷たい光があるのが感じ取られ、少し怖い気持ちがした。一ノ瀬さとしと酒見正も、沢木キョウの空手の技や英語、それに急に先生がその場に現れたことで、さっきまでの勢いを一気にをなくしたようで、「わかりました。いこうぜ、正」と一ノ瀬さとしが酒見正に言って、二人はさっとどこかに消えていった。
「ふうー。あーよかった。一時はどうなることかと思った」と、酒見正と一ノ瀬さとしが遠くに行ってから、ほっとした表情で真中しずえが口を開いた。
「しずえちゃん、無理しすぎ。あれ、一ノ瀬君、本当に殴るつもりだったよ。」
「え、カンナ、あのあたりから見てたの?」
「うん、立花先生と走ってきたから、しずえちゃんが一ノ瀬君に話してる内容も聞いてたよ。」
「じゃあ、私が殴られそうなの黙って見てたってこと?」と、ちょっといたずらっぽく頬をふくらませながら真中しずえが言うと、「ときには痛い目にあわないと無茶ばかりするからね」と、いたずらっぽい笑みを返しながら空木カンナは答えた。
「もう!」
「冗談よ。本当は、これを使うつもりだったの。」
と、手にした笛を見せた。体育の授業とかで使う笛だった。
「これ、保健室にあったから立花先生に借りたの。一ノ瀬君や酒見君が何かしてきたら、この笛で大きな音を出せば彼らは驚くし、誰かが様子を見にきてくれるかな、って思って。だから、しずえちゃんが一ノ瀬君を殴ろうとしたとき、これを口にくわえたんだ。でも、沢木君がしずえちゃんと一ノ瀬君の間に入ってきたから、笛は鳴らさなかったの。」
「そうだったんだ。でも、沢木君すごかったね。空手やってたんだ。あの一ノ瀬君が手も足もでなかったもんね。」
「たまたまだと思うよ」と、沢木キョウは、真中しずえと空木カンナの会話に加わる。「一ノ瀬君、油断してたから意表をつかれただけだよ。あれだけ身長の差があれば、彼が本気でかかってきたら勝てるかどうかわからないよ。だから、空木さんが先生が連れてきてくれて助かったんだ。」
「そうなのかなぁ」と、真中しずえは納得しきれていない様子だったが、ふと何かを思いだしたように、「あ、羽加瀬君は大丈夫だった?私たちが来る前になにか痛いことされなかった?」と羽加瀬信太に向かって話しかけた。
「う、うん、大丈夫。みんなにまた迷惑かけちゃってごめんね。」と、声に力はなかったものの、頑張って笑顔を出して羽加瀬信太はそう答えた。
「え?またってどういうこと?」と、真中しずえが聞くと、「えっと・・・それは・・・」と、羽加瀬信太は何て答えるべきかと言い淀んだ。
その様子をみて、「今朝のことかな?」と、空木カンナが助け舟を出すと、「え・・・あ・・・う、うん」と、羽加瀬信太が返事をした。
すると真中しずえは、「あ、あれのことね。全然迷惑じゃないわよ。私たち、同じ科学探偵クラブの仲間じゃない!」と元気よく言った。
「あ、ありがとう・・・」と答える羽加瀬信太に笑顔で答えた真中しずえは、「でも、あの二人には困ったものね。まあ、さっきの様子なら、もう羽加瀬君にはからんでこないんじゃない?こっちには強いボディーガードもでいるんだし」と、真中しずえが沢木キョウの方を向いてそう言った。
「いや、だから、そう話は単純じゃないように思うんだけど・・・」とちょっと困ったように沢木キョウが言ったが、「全然大丈夫よ!」と、真中しずえは自信満々にそう答えた。
「いや、でも、僕もキョウ君と同じ考えだよ。さっきあの二人がここを離れるとき、一瞬だけど酒見君はすごい目でこっちを睨んでたよ」と田中洋一が続けて言うと、「そうね、一ノ瀬君は単純そうだけど、酒見君はちょっと執念深いというか根に持つタイプだと思うよ。しばらくはまだ注意が必要な気がするな、私は」と空木カンナも同意した。
「またまたーみんな心配性なんだから。大丈夫よ、きっと。また何かあれば、みんなで一緒にやっつけちゃいましょう」と、パンチやキックを出す真似をしながら真中しずえは明るく笑いながらそう言った。
「こらこら、女の子だって暴力はダメですよ」と優しく立花美香がたしなめると、「あ、先生がいたんだった。今のはウソでーす。聞かなかったことにしてください」と言って、みんなの笑いを誘った。
「はいはい。じゃあ、そろそろお昼休みも終わるし、みんな教室に戻ってくださいね。あ、空木さんは私と一緒に来てね。上履きの底を拭かないといけないので」と立花美香が言うと、その場は解散となった。
そして、その日の午後の授業および放課後も何事もなく時間が過ぎていった。しかし、次の日の朝、再び教室内で問題が起きるのであった。
***