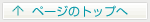SFミステリー小説:永遠の秘密
TweetSFミステリー小説:永遠の秘密
第二章:科学探偵クラブ(1)
相葉由紀(あいば・ゆき)は六年三組のクラスの中で目立たない子だった。彼女は一人で本を読むのが好きで、休み時間はいつも何かの本を読んでいた。放課後も学校の図書室で下校時間ぎりぎりまで本を読んで帰ることもあった。
この日は激しい雨と雷の日だった。午後の授業のあとの帰りの会が終わったときも雷雨は続いていた。
相葉由紀の自宅は学校から少し離れたところにあったので、雨が少し弱くなるのを期待して、彼女は図書室で少し本を読んでから帰宅することにした。
この学校には図書室が二つある。
一つは旧校舎に、もう一つは新校舎にある。当然、新校舎の図書室の方が広くて綺麗だ。ゆったりと座れるソファーもあるし、蔵書の数も旧校舎の図書室とは比べものにならないくらい多かった。また、普通の小学校とは違い、新校舎の図書室には漫画も並べられていたので休み時間はいつも混んでいた。大半は漫画を目当てにくる児童であり、ほとんどの漫画はいつも貸出中で本棚に残っている漫画の数は少なかったのだが。
逆に、旧校舎の図書室にはほとんど児童が訪れることはなかった。それは、新校舎の図書室よりも狭くて古くて漫画がない、ということとは別の理由もあった。旧校舎の図書室の隣には四畳ほどの小さな図書準備室があった。この準備室には、もう誰も読まなくなった古い本や、旧校舎・新校舎の図書室に並べきれなかった本などが保存されていた。
図書準備室に廊下から入るドアはなく、旧校舎の図書室の奥にある狭いドアからしか入ることができなかった。そのドアには古いタイプの南京錠がかけられており、その鍵はパスコードである四桁の数字を正確に合わせないと開くことはできなかった。しかし、いつの頃からか、図書準備室には誰も入らなくなり、南京錠の鍵のパスコードは教師を含めて誰もわからなくなってしまっていたようだった。
そんな開かずの図書準備室には、なにやら幽霊が潜んでいるという噂が数年前から学校全体に広がっていた。だから、今ではほとんど誰も旧校舎の図書室には入らなくなっていた。
しかし、相葉由紀はこの日の放課後に旧校舎の図書室に行くことにした。新校舎の図書室が、雷雨のためかとても混んでいて、ゆっくりと静かに読書に没頭できなさそうだったからだ。それに、久しぶりに旧校舎の図書室に行ってみることで、なにか面白い本が見つかるかもしれない、との期待もあった。
もちろん相葉由紀は幽霊の噂は知っている。しかし、幽霊なんて非科学的なものが存在するはずがないと思っていたので、この日は幽霊の噂のことなど思い出しもせずに旧校舎の図書室に入っていった。
「あ、やっぱり誰もいない。静かでいいな。」と、思わず口にして相葉由紀は推理小説が並ぶ本棚に向かった。そして、前から読もうと思っていたアガサクリスティーの『そして誰もいなくなった』の本を選び、図書室の奥の方の椅子に座って読み始めた。
夢中になって本を読んでいたとき、ふと近くで誰かが話しているのが聞こえた。
「え、誰かいるの?」と、相葉由紀は少しおどおどした様子で聞いてみた。幽霊の噂のことを思い出してしまったのだ。だが、返事はなかった。
「気のせいかな?気のせいよね。きっと雨の音を聞き間違えただけだわ。」と、不安な気持ちを振り払うかのように、わざと少し大きな声で独り言を言った。と、そのとき「ひゃっ!」という声がはっきりと相葉由紀の耳に聞こえた。
「今のは絶対に聞き間違えじゃないわ。誰かいるのかしら。もしかして本当に幽霊?」と、相葉由紀がすぐに図書室から逃げようかと悩んでいると、『ピカッ!ガラガラガッシャーン』と窓の外が光ると同時に大きな雷の音が聞こえた。近くに雷が落ちたようだ。それとほぼ同時に、「うゎー!!!」という叫び声が聞こえ、その直後に誰もいないはずの図書準備室から大きな音が聞こえた。
相葉由紀は驚きと怖さで気が動転し、とりあえず自分のランドセルだけを手にとって急いで図書室を抜け出て、そのまま傘もささずにずぶ濡れのまま走って家まで帰った。読みかけの本と彼女のお気に入りの筆箱やノートを図書室に忘れてきたのに気づいたのは、家に帰ってからのことだった。
***
翌日、いつもと違う筆箱を机の上に置いてるのに気づいた真中しずえ(まなか・しずえ)が相葉由紀に話しかけてきた。
「おはよう。今日は新しい筆箱を持ってきたの?それ可愛いね。」
「これ、私が3年生のときまで使っていた古い筆箱なの。いつもの筆箱はちょっとなくしちゃって・・・。」
「そうなんだ。前に使っていたのにすごく綺麗だね。由紀ちゃんは物を大事に使ってるんだね。」
「う、うん・・・。」
「どうしたの?なんか元気ないみたいだけど。」
「ううん、大丈夫。」
「本当に?私ができることがあったら言ってね。」
「うん、ありがとう・・・。実はね・・・。」
と言って、相澤由紀は昨日の放課後に旧校舎の図書室で起きた出来事を話した。
「そうだったんだ。筆箱、そこの机に置いてきちゃったんだね。」
「うん、読みかけの本とかノートとかも置きっぱなしのままなんだ。今日の朝、この教室に来る前にその図書室に寄りたかったんだけど、何だか怖くて・・・。」
「じゃあ一緒に行こうよ。」
「え、ほんとに?」
「うん。今から行ったら朝の会に間に合わないかもしれないから、二時間目と三時間目の授業の間の15分休みのときに走って取りに行こうよ。」
「ほんとにいいの?怖くない?」
「大丈夫大丈夫。実はね、この間、私とカンナで科学探偵クラブを作ったんだ。」
「科学探偵クラブ?」
「ほら、カンナと私は科学クラブに入ってるでしょ。それでね、このあいだ不思議な現象や謎を科学の力で解き明かす科学探偵をしてみると楽しいかもね、って話してたの。だから科学クラブの下部組織として科学探偵クラブを作ろうとしてるんだ。」
「そ、そうなんだ。」
「だけどね、不思議な現象や謎って、実は身近にはあんまりないんだよね。だから、科学探偵クラブの事件簿第一弾として、この旧校舎の図書室に現れる幽霊の謎を解いてみようかな、って由紀ちゃんと今話していて思ったんだ。」
「そっか。」
「学校の七不思議みたいで面白くない?」
「どうかな。私はちょっと怖いけど・・・」
と、相澤由紀が言ったところで、近くの席にいた悪ガキ二人組の一ノ瀬さとし(いちのせ・さとし)と酒見正(さかみ・ただし)が馬鹿にしたような口調で「学校の七不思議だってよ」「そんなの昭和時代でしか盛り上がんねーよ」と、口々に言って真中しずえに絡んできた。
「あんたたち、またそんな悪口ばかり言って。」
「悪口なんかじゃねーよ。今さら学校の七不思議なんて流行んねーよ、って言っただけだろ。」
「そんなこと言って、本当は怖いんじゃないの?」
「な、何言ってんだよ。怖いわけねーだろ、そんな噂。幽霊なんているわけねーし。」
「私もそう思うよ。だから科学の力で旧校舎の幽霊の謎を解き明かそうとしてるのよ。」
「無理無理。お前なんかじゃ幽霊の謎はわかるわけないじゃん。」
「言ったわね。由紀ちゃんが見た幽霊を絶対に捕まえてみせるから!」
「私、幽霊は見てないし、別に捕まえてほしくもないけど・・・」と、小さな声で相澤由紀が真中しずえに言った。
「え、そうなの?でも幽霊っぽいのが近くにいたのは確かなんだよね。単に自分の目で見てないだけで。私、その謎を解いてみせるわ、由紀ちゃんとカンナと一緒に。」
「え、私も一緒に幽霊の謎を解くの?」と相葉由紀が驚いた声で言ったとき、少し離れた席でランドセルから教科書を出していた空木カンナも全く同じセリフを言ったのは真中しずえの耳には届かなかった。
***