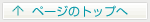SFミステリー小説:永遠の秘密
TweetSFミステリー小説:永遠の秘密
第二章:科学探偵クラブ(2)
2時間目の社会科の授業が終わったあと、真中しずえは相葉由紀と空木カンナと一緒に早足で旧校舎の図書室に向かっていた。
「私、実は旧校舎に入ったことないの」と、空木カンナは言った。「そっか、カンナは去年この町に引っ越してきたんだもんね。たしかに5年生のときは旧校舎に行くことはなかったね」と真中しずえが答える。
「うん。去年の授業は全部、私たちのクラスがある新校舎だったし、あえて旧校舎に行く理由もなかったから。でも、相葉さんは旧校舎にはよく行ってるの?」
「ううん、そんなには行かないよ。旧校舎の古い図書室に行くときくらいかな。」
「旧校舎の図書室と新校舎の図書室ってそんなに違うの?私、去年この学校に転校してから実はまだ一回も図書室には行ってないんだ。」
「え、そうなの?もったいないよ。色んな本があるんだよ。読書は嫌い?」
「大好きだよ。本はいいよね。自分が知らなかった新しい知識が入るし、他の人が体験したものも吸収できるし、色々な人生を送った気になれるわ。」
「そうよね。私も読書は大好きなの。でも、今の空木さんのセリフ、すごい大人っぽいね。」
「でしょー!」と、真中しずえが二人の会話に割って入る。
「カンナってこんなに可愛らしい女の子なのに性格は大人の女の人みたいなの。」
「またその話?しずえちゃんっていつも私のことを年上扱いするんだよね。大人の女ならまだいいけど、時々オバさん扱いすることもあるんだよ。」
「え、私そんなこと言ったっけ?ごめーん。」
「あんまり反省してるようには見えないけど?」
「反省してるって。ごめんね。でも私、本当にカンナの大人っぽいところが大好きなの。尊敬しているお姉さんって感じ。」
「ま、今日はそのくらいで許してあげるわ。」
「ぷっ」と相葉由紀は吹き出した。
「どうしたの?」と真中しずえが聞く。
「なんか二人のやり取りが面白くて。すごく仲の良い姉妹みたい。私、空木さんがこういう性格だって知らなかった。」
「そうなのよ。空木さんってクラスでは静かにしてるでしょ。でも、すごく頼れるお姉さんキャラなのよ、本当は。お人形さんみたいに可愛らしい見た目なのに。」
「いいなー、私もそんな友達が欲しかったな。私、友達を作るのが苦手で。だからいつも学校では本を読んでたの。」
「私たちもう友達だよ。だって由紀ちゃんも科学探偵クラブの一員でしょ。これから幽霊の謎を一緒に解くんだから。」
「え・・・?」
「しずえちゃん、相葉さんが困ってるよ。勝手に科学探偵クラブの一員にしたら可哀想よ。私だって、知らずに科学探偵クラブの一員にされてびっくりしたんだから。」
「カンナちゃんは私の相棒だから当然!」
「またそうやって誤魔化す。まあいいわ、図書室に着いたから中に入ろうか。私、ここには初めて入るからちょっとドキドキするわ。」
「由紀ちゃんは昨日どこら辺の席に座ってたの?」と、図書室に入ろうとしていた真中しずえが聞いたのだが、相葉由紀は図書室の入り口で立ち止まって下を向いたまま返事をしなかった。
「どうしたの?」
「昨日のことを思い出しちゃったの。図書室に入るのが怖いの。」
「大丈夫だよ。入ろ?」
「でも・・・」
「じゃあ、私が見てくるね。どこら辺に座ってたの?」と、空木カンナが聞いた。
「え、そんなの悪いよ。」
「大丈夫よ!」と、真中しずえが空木カンナの代わりに答えるのを聞いて、空木カンナは苦笑いをした。
「えっと、一番奥の席だった。図書準備室にはいる扉の近く。」
「じゃ、行ってくるね」と言って図書室に入っていった数秒後、図書室の奥の方から「あったよー。幽霊も人間も誰もいないよー」という空木カンナの声が聞こえた。
「由紀ちゃんの筆箱あったみたいよ。一緒に行こう」と言って、真中しずえは相葉由紀の手をとって図書室に入っていった。相葉由紀が昨日座っていた席のところにつくと、一足先に図書室に入っていった空木カンナは図書準備室へと続く扉の前にいた。
「カンナ、何してるの?」
「私、ここに入るの初めてだから、ちょっと散策。これが幽霊がいるって言われてる図書準備室への入り口なのね。」
「そうね。やっぱり鍵がかかってるね。」
「うん。数字を回して鍵を開けるタイプの南京錠か。『0』から『9』までの目盛りがついたダイヤルが4つ。組み合わせは一万通りか。ランダムに試しても開かないわね。」
「空木さん、計算が早いんだね」と、自分の筆箱とノート、それに昨日読んでいたアガサクリスティーの『そして誰もいなくなった』の本を手にした相葉由紀が、真中しずえと空木カンナに近づきながら言った。
「そうかな。『10』の四乗だから、そんなに複雑な計算じゃないよ」と空木カンナが答えると、「よんじょう?」と不思議な顔をして相葉由紀が返した。
「カンナ、それって中学で習う内容じゃないの?」
「あれ、そうだっけ?」
「もう、カンナって本当に小学六年生なの?」
「あー、またそうやって年寄り扱いしてる。」
と、そのとき『キーンコーンカーンコーン』と三時間目の授業が始まるチャイムの音が鳴り始めた。
「あ、まずい」と真中しずえが言って、走り出した。「幽霊探しの続きは放課後にしよう」と言いながら走る真中しずえのあとを追っていた相葉由紀は、「なんかとんでもないことに巻き込まれちゃったな」と思いつつも、これまでとは少し違う学校生活に少し心がウキウキしていた。
***
放課後、真中しずえ・空木カンナ・相葉由紀は旧校舎の図書室にいた。彼女たちの予想通り、その図書室には誰もいなかった。彼女たち三人と、彼女のクラスメートである田中洋一(たなか・よういち)と沢木キョウ(さわき・きょう)を除いては。
「というわけで、幽霊の謎を科学の力で解いてみよう!」と、真中しずえは他の四人に向けて、そう檄を飛ばした。
「えっと・・・、なんで僕とキョウ君が呼ばれてるんだろうか」と、田中洋一が戸惑いながらそう聞いた。
「え、今の説明を聞いてなかったの?昨日、由紀ちゃんがここで幽霊に会った、いや幽霊が暴れる音を聞いたんだよ。」
「その話はわかったんだけど、幽霊の謎を解くって何なの?しかも科学の力をどう使うの?」
「それをみんなで考えるのよ。科学探偵クラブの一員でしょ。」
「僕はいつから科学探偵クラブの一員になったの・・・?」
「今日からよ!」
「・・・」と、絶句する田中洋一の横で、意外にも沢木キョウは「まあ、せっかくだし、面白そうだからやってみようよ」と田中洋一を元気づけるセリフを口にした。
「さすがキョウ君。話がわかるね。」
「で、科学の力を使って何を明らかにしたいの?」
「いい質問だね。じゃあ逆に聞くけど、科学で一番大事なのって何だと思う?」
「いきなりのオープンクエスチョンか。何だろう。洋一君はわかる?」
沢木キョウにそう聞かれた田中洋一は「うーん、注意深い観察力?」と少し自信なさげに答えた。
「なかなか良い線いってるね。注意深い観察力大事だけど、もっと重要なことがあるんだな」と勿体ぶりながら真中しずえが言った。
「えー、じゃあなんだろう」と田中洋一が悩んでいると、「再現性かな?」と空木カンナが横から助け舟を出した。
「正解!」と、親指を上に突きだした『グッジョブ』のポーズをしながら真中しずえが言った。そして、「再現性って何?」と聞いてきた相葉由紀の方を向いて、真中しずえは「科学はね、同じ条件が揃っていたら、いつでも同じ結果になることになっているの。それを再現性のある事象って呼ぶの。科学にはいつも決まったルールがあって、そのルールのもとに物事が動いてるんだよ。幽霊だって、もしそれが本当にいるのなら、何らかのルールがあるはず。だから、まずはね、由紀ちゃんが昨日の放課後に幽霊の音を聞いたときと同じ条件を作ったら、昨日みたいなことがまた起きるかどうかを確認してみたいと思ってるの」と答えた。
「なるほど、それは面白いアプローチだね」と沢木キョウが言った。
「でしょ!」と得意気に真中しずえが言って、相葉由紀に「じゃあ由紀ちゃん、出来るだけ昨日と同じことをやってみて」と頼んだ。
相葉由紀は「うん」と言って、少し考えてから、図書室に入ってくるところから始めた。まず、図書室の奥の机の横まで進みランドセルを椅子の横に置いた。そのあと、ランドセルから筆箱を出して机の上におき、アガサクリスティーの『そして誰もいなくなった』の本があった本棚のところまで行き、その本を本棚から取り出す振りをしてから、ランドセルを置いていたところまで戻った。そして、昨日と同じようにアガサクリスティーの『そして誰もいなくなった』を読み始めた。
「このあと、二十分くらい本を読んでいたんだけど、どうすればいい?」と相葉由紀は聞いたところで、空木カンナが「ねえ、昨日は雨がすごく降ってたじゃない。でも今日はとっても良い天気よ。これって同じ条件が揃ってるって言えるのかな?」と言った。
「あ、そうか。全く同じ条件にしないといけないのかな。でも、天気まで同じにするのって難しいよね・・・。ねえ、由紀ちゃん、そこで読んでいたら幽霊の音ってどこから聞こえてきたの。」
「えっと、後ろの方かな?だから、図書準備室の方から聞こえてきたような気がする。」
「図書準備室の中からの音っぽい?」
「どうだろう。雨の音も激しかったし、雷も鳴ってたからはっきりとはわからないかも。」
「そうかー。他に何か気になったことある?」
「あ、そういえば、近くで雷が落ちたようなすごい音がしたときに、叫び声みたいなのが聞こえて、そのあとで何か物が落ちるような音が聞こえたの。」
「あ、わかったかも!」と田中洋一が嬉しそうな声でそう言って、みんなの会話に入ってきた。
「何がわかったの?」と真中しずえが聞くと、「幽霊の謎だよ」と得意気に言い、続けて「その幽霊は雷が苦手で、雷が落ちた音に驚いて叫び声をあげて走り出したんだよ。そして、何かにつまづいて転んだんだ」と自分の推理を力強く説明した。
一瞬の静けさが図書室に訪れたあと、呆れた口調で真中しずえが「それ本気で言ってるの?」と聞いてきた。
「え・・・僕、何かおかしなこと言った。」
「幽霊は足がないの。だから走らないの。」
「あ、たしかに。じゃあ雷の音に驚いて浮かび上がったから天井に頭をぶつけたとか?」
「幽霊は壁とか天井とかすりぬけられるの。それに、幽霊は雷を怖がらないものなの!」
頭を抱える真中しずえの横で沢木キョウが「洋一君のアイデアは面白いと思うよ」と田中洋一をかばい、続けて「音を出したのは幽霊じゃないとは思うけど、もしかしたら図書準備室に誰かがいたという可能性は十分にありえると思うよ」と言った。
すると、空木カンナが、「私もそう思ったの。でも、図書準備室に行くには、この図書室にあるドアからしか入れないんだよね。それで、そのドアには南京錠がかかっている、と。私は去年この学校に転校してきたから良くわからないんだけど、このドアって本当に噂通りの開かずの扉なの?」と、真中しずえに聞いてきた。
「私も詳しくは知らないんだよね。由紀ちゃん何か知ってる?」
「え、私も知らないかも。こっちの図書室には月に一回くらいしか来てないけど、これまでこのドアが開いていたことも、誰かがドアを開けたのも見たことないの。」
「いつも南京錠はかかってた?」と、空木カンナが違う質問をしたが、「あんまり詳しくは見てないかも。本を探したり読んだりすることに集中してたから。ごめんね」と相葉由紀は小さな声で答えただけだった。
「ううん、謝らないで。いつも開いてないドアになんて普通は気を配らないと思うから。でも、そうだとすると、やっぱりを解く鍵は図書準備室に入れるかどうか、だね」と真中しずえが言うと、「幽霊の謎を解く鍵はこの南京錠だね。鍵だけに!」と田中洋一は笑いながら明るい声で言った。しかし、笑っていたのは田中洋一だけだった。
***