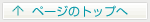SFミステリー小説:永遠の秘密
TweetSFミステリー小説:永遠の秘密
第二章:科学探偵クラブ(3)
次の日は再び雨だった。給食の後の休み時間に、真中しずえと空木カンナは、六年三組の担任である池田勇太(いけだ・ゆうた)のところに旧校舎の図書準備室へ入る方法を聞きにいった。池田勇太は二人のクラスの担任であるだけでなく、科学クラブの顧問にもなっている。
昨年の夏休みには、真中しずえと空木カンナの研究プロジェクトを熱心に指導していた。そのため、真中しずえと空木カンナは、池田勇太に対しては比較的自由に物を言える立場にあった。また、池田勇太も、あまり好ましいことではないと思いつつも、真中しずえと空木カンナの二人には他の児童とは違った対応をすることがあった。
「池田先生、お願いがあるんです!」と、真中しずえは話を切り出した。
「またお願いか。今回のはなんだ?科学クラブで新しい実験をしたいとかそんなのか?」
「違います。旧校舎の図書室の横にある図書準備室に入りたいなと思ってるんです。」
「なんでまたあんなところに。宝探しでもしてるのか?」
冗談を言って笑わせようとした池田勇太だったが、真中しずえは笑いもせずに「幽霊の謎を解きたいんです!」と、一歩近づいてそう言った。
「幽霊?一体なんの話をしてるんだ?」と不思議そうな顔をしている池田勇太に、真中しずえと空木カンナは一昨日の放課後に相葉由紀の身に起きた出来事と昨日の放課後にみんなで図書室に行ったときの様子を説明した。
「なるほど、君たちが言いたいことはわかった。でもなあ、そんな理由であそこの鍵を開けるのはどうかと思うな。」
「そこを何とかお願いします。」
「幽霊がいるかどうかを確かめるためにって、そんなの理由にはならないよなあ。君ら科学クラブに入ってるんだろ。幽霊なんて、そんな非科学的なこと信じるのか?」
「自分の目で確かめてこその科学クラブですよ、先生。」
「うーん、とは言ってもなあ。」
「あ、そうだ」と、空木カンナが池田勇太と真中しずえの会話に割って入る。
「池田先生、たしか去年の終わりごろに、『来年は図書委員の担当をするのか〜』って言ってましたよね。」
「おう、よく覚えてるな。そうなんだよ、今年は図書委員の担当なんだよな。一年ごとの持ち回りで、まあこう言っちゃなんだが、特に大きな仕事はないからいいんだけどね。」
「じゃあ、池田先生は今、図書委員の担当なんですよね?旧校舎の図書準備室の本の整理をするって名目で、その部屋に私たちと一緒に入ってくれませんか?何なら掃除とかもしちゃいますよ。」
「お、それは良いアイデアだな。掃除もしてくれるんなら、俺にとってもありがたいな。」
「じゃあ、早速今日の放課後に行きましょう。」
「おう、いいぞ。でも、掃除をするんなら、君ら二人だけだと大変じゃないのか。もっと人手が入りそうだが。帰りの会で掃除を手伝ってくれる人を募集するか。まあ、放課後にわざわざ掃除したいなんて奴はいないかもしれないけどな。」
すると、「大丈夫ですよ、先生。科学探偵クラブの人は強制参加なので!」と、嬉しそうに真中しずえが言った。
***
「で、何で僕も掃除を手伝うことになってるの?」と、少し不満そうな顔で田中洋一がぼやいた。
場所は旧校舎の図書室。半ば強引に科学探偵クラブの一員にさせられた田中洋一と沢木キョウは、その日の放課後に行う掃除メンバーに加えられてしまっていた。また、実際に『幽霊の音』を聞いていて、同じく科学探偵クラブの一員となってしまった相葉由紀も掃除に参加することになった。六年三組の帰りの会で担任の池田勇太が掃除ボランティアの募集を行なったが、予想通り誰も手は挙げなかった。
「これだけいれば十分ね」と真中しずえが話し始める。
「あれ、カンナどうしたの?」
「この南京錠、実は鍵が壊れてたりしないかなって思って色々ためしてみてるの。」
「開きそうなの?」
「ううん、全然。」
「今、池田先生が職員室で鍵の番号をチェックしてるから、すぐに開けられるよ。」
「そうね。でも、何だかちょっと不思議なのよね。」
「何が?」
「ここって何年も使われてなかったんだよね。」
「そうだと思うよ。池田先生もそんなこと言ってたし。」
「でも、その割にはこの南京錠は新しく見えるのよね。古いタイプの鍵であるのは確かなんだけど、この鍵自体はつい数ヶ月前に買ったみたいな感じ。」
「気のせいよ、そんなの。ほとんど使われてなかったから新しく見えるだけじゃないかな。」
「そうかなー」と、真中しずえの言うことにあまり納得していない様子の空木カンナだったが、次の瞬間、誰かが図書室に入ってくる足音が聞こえてきた。
「池田先生が来たみたい」と相葉由紀が言ったが、そこに姿を現したのは、同じクラスの羽加瀬信太(はかせ・しんた)だった。
「あの・・・僕も掃除を手伝ってもいいかな?」と聞いてきた羽加瀬信太に、「もちろん!ありがとう」と真中しずえは答える。その返事を聞いて羽加瀬信太はとても嬉しそうだった。
と、そこに小さな手帳を手にした池田勇太がやってきた。
「やあ、待たせてごめん。お、信太も来てくれたのか。これだけいれば掃除には十分だな。」
「先生、遅いですよ。」
「すまんすまん。鍵の番号を見つけるのに苦労してな。やっぱり、ここ数年は誰も使ってなかったみたいだったよ、その図書準備室。」
「え、じゃあ鍵の番号は見つけられなかったんですか。」
「いや、それは大丈夫。きちんと記録は残っていたよ。」
「番号は何だったんですか?」
「うーん、本当は児童には教えちゃいけないことになってるんだけどな。まあいいか。誰にも言うなよ。」
「言わないから大丈夫です。科学探偵クラブだけの秘密です!」
「科学探偵クラブって何?」と、横から羽加瀬信太が聞いた。
「あ、そうか。信太君はこないだいなかったもんね。えっとね、科学の力で不思議な謎を解いていくグループなんだよ。」
「面白そうだね。」
「でしょ。信太君ももう科学探偵クラブの一員ね。」
「え、僕も入っていいの?」
「もちろん。で、今日は幽霊の謎を調べるために来たんだよ。」
「幽霊の謎?図書準備室の掃除じゃなくて?」
「ほら、信太も何言ってんだこいつ、って顔してるじゃないか」と池田勇太は言った。「幽霊なんていないんだよ。さあ、掃除掃除。鍵を開けるぞ。」
「先生、ひどい」と言いつつも、池田勇太の発言は全く気にしていない様子で真中しずえは「で、鍵の番号はなんです?」と聞いた。
「『0123』の四桁だよ。他の奴らには言うなよ。」
「え、何その適当な番号。」
という二人の会話を聞きながら、ドアに一番近いところにいた空木カンナが南京錠を開けようとする。だが、その鍵は開かなかった。
「先生、開かないですよ。」
「ほんとか?『0123』だぞ。」
「『0123』に合わせましたが開きません。」
「おかしいな」と言いつつ、今度は池田勇太が自分でも試してみる。そして、「あれ、やっぱり開かないな。おかしいな。メモに書き間違えたかな。もしかして、『0321』だったかな。うーん、これでも開かないか」と言いながら、ガチャガチャと色々と試してみた。しかし、それでも南京錠は開かなかった。
「先生、どうしますか?」と空木カンナが聞いた。「仕方ない。職員室に行って番号をもう一回見てくるよ。それで、もしそこに『0123』と書いていたら、用務員室かどこかで鍵を壊す道具を持ってくることにしよう。誰かが鍵の番号を記録するときに間違ったのだとしたら、この鍵はもう使えないからな」と言って図書室を去っていった。
「さてと、私たちはその間どうする?」と真中しずえが聞いたとき、羽加瀬信太はドアのところに歩いていって何やら南京錠をガチャガチャしていた。
「信太君、何してるの?もしかして、泥棒みたいに鍵を開けられたりするの?」と、真中しずえが聞くと、「ううん、もちろん、そんなことはできないよ。でも、何か適当に番号を入れて開かないかなって試してるの」と、羽加瀬信太は答えた。
「えー、そんなの無理だよ。」
「うん、僕もそう思うよ。でも、池田先生が戻ってくるまで暇だなと思って。さっきは『1029』を試してみたんだ。僕の誕生日は十月二十九日だから。」
「開いた?」
「ううん、ダメだった。さすがにそんなに都合良くはいかないかな。」
「ねえ、私の誕生日は七月十二日なの。『0712』を試してみてくれる?」
と、真中しずえが自分の誕生日の四桁を伝えると、「うん、いいよ」と言いながら、羽加瀬信太がその数字を合わせた。すると、『ガチャ』と小さな音がして南京錠が開いた。
「え?」
「どうしたの?」
「開いちゃった。」
「ほんと?『0712』で開いたの?」
「うん・・・」
「じゃあ、ドアを開けられるってこと?」
「たぶん・・・」と言いながら、羽加瀬太郎が南京錠を外してドアノブをゆっくりと回すと、『ギギィ』と音がしてドアが開いた。図書準備室の中は真っ暗で、少し湿った匂いがした。
「ど、どうしよう・・・」と羽加瀬太郎がみんなの方を向いて言うと、真中しずえは「中を見てみるしかないよね」と答えた。
「でも、勝手に入ったら怒られちゃうんじゃない?それに、ちょっと怖い」と相葉由紀が言った。
しかし、相葉由紀の言ったことは聞こえなかったのか、空木カンナはドアを全開にして図書準備室に体を半分いれた状態でドア付近を見回し、右手で何やら探していた。そしてすぐに『カチャ』と音がして図書準備室の電気がついた。
「うん、電気はちゃんとつくね」と独り言のように空木カンナが言うと、沢木キョウが空木カンナの横までいって図書準備室の中を見た。
「やっぱり狭いね。」
「そうね、しかも古い校舎だけあって、この部屋の作りも古臭い感じ。」
「ここを掃除するのはちょっと大変かな。」
「私もそう思う。この人数が全員入るのも少し厳しいくらいだしね。」
「私たち、掃除に来たんじゃないのよ」と、空木カンナと沢木キョウの会話に、真中しずえが割って入る。そして、「幽霊の謎を解かなくちゃ。私も中にいれて」と言って、二人の間を通って図書準備室に入っていった。
それに続いて羽加瀬信太も、少しおどおどして天井を何度もチラッと見ながら、じめっとした図書準備室の中に入っていった。だが、相葉由紀は「私はちょっと怖い」とドアから少し離れたところで立っていて、田中洋一も「中は狭そうだから僕も外にいるね」と言って相葉由紀の近くから図書準備室の中を見ているだけだった。
図書準備室の中に入った四人が棚の本とかテーブルに乱雑に置かれていた紙の束を見ていたところ、突然「キャッ」という声が真中しずえから発せられた。
「どうしたの?大丈夫?」と、おどおどした声で相葉由紀が隣の図書室から聞いてきた。
「大丈夫大丈夫。なんか床が濡れていて少し滑ったの。」
「え、もしかして血?」と田中洋一が言うと、「そんな怖いこと言わないで」と横から泣きそうな顔で相葉由紀が言ってきた。
「血じゃないわよ。ただの透明な水っぽいの。でも、なんで濡れてるのかしら、この床。」
「幽霊がいた場所は、その後に床が濡れてるって聞いたことあるけど、もしかして本当に幽霊が・・・」と田中洋一が喋り始めると、「やめて」と目に涙を浮かべながら相葉由紀が少し大きな声で田中洋一の発言をさえぎった。
「ごめん」と田中洋一が答えるのとほぼ同時に、図書準備室の中で「雨漏りしてるね、この天井」と上を指差しながら空木カンナは言った。指をさした先は真中しずえのいる当たりの天井で、「え、ほんと?」と言いながら上を見た真中しずえの目の前を水滴が落ちてくる。『ピチャ』と小さな音がした。
「こっちも雨漏りしてるっぽい」と図書準備室の奥の方にいた羽加瀬信太が言う。「古い建物だからね。本とかにダメージがないといいけど」と沢木キョウが言ったところで、「お、ドアが開いたのか?」と池田勇太の声が聞こえてきた。池田勇太が図書室に戻ってきたので、図書準備室にいた四人はいったん図書室に出てきた。
「その鍵、結局あいたのか?やっぱり『0123』だっただろ?」
「『0712』でした。」
「『0712』?」
「そうです、私の誕生日でした。」
「『0712』?真中の誕生日?何だそれ。職員室にあった記録では、やっぱりこの鍵の番号は『0123』だったぞ。」
「ほんとですか?でも、実際に『0712』で開いたんですよ。池田先生も試してみますか?」
池田勇太が真中しずえから南京錠を受け取り、『0712』に数字をセットすると『ガチャ』と音がして確かに鍵は開いた。
「あれ、ほんとだ。おかしいな。誰かが新しく鍵を変えてたのかな。まあいいや、あとで職員室の記録用紙を書き換えておくか」と言って、池田勇太は自分の小さな手帳に『0712』の数字を書いた。
「で、中に入ってどうだった?幽霊とやらはいたか?」
「幽霊はいませんでした。でも、雨漏りはしてました。」
「雨漏り?」
「はい、天井から。少なくとも2ヶ所。」
「どれ、ちょっと見てみるか。」
そして、真中しずえから雨漏りをしていることを聞いた池田勇太は図書準備室の中に入る。そして、真中しずえがその後に続いた。
図書準備室の中で真中しずえが指差した天井を見て、池田勇太は「あー、たしかにこれは雨漏りしてるな。業者を呼ばないといけないな」とちょっと面倒くさそうに言った。そして自分の腕時計を見て「もう4時前か。明日電話するかな。いや、電話だけでも今日しておくか。明日来てもらえるかもしれないしな。ん、ちょっと待てよ。今日は木曜日だよな。ということは明日の放課後は会議か。じゃあ、業者に来てもらうのは早くても来週の月曜日か。電話も明日にしようかな。うーん、でもやっぱり・・・」と、独り言のようにブツブツと言っていた。
「池田先生、掃除はどうします?」と真中しずえが聞くと、ハッと我に戻った池田勇太が「そうだな、雨漏りしてるから床も少し濡れてるな。今日はちょっとやめておこうか。俺は職員室に戻って雨漏りを修理してくれそうな業者の連絡先とか調べてみるよ」と答えた。
「図書準備室の中をもう少しだけ見ててもいいですか?」
「なんだ、まだ幽霊を探してるのか?」
「いえ、そういうわけではないんですが。」
「少しならいいよ。でも床が濡れてるから気をつけるんだぞ。あと、きちんと電気を消して鍵もかけておいてくれよ。」
「はい、わかりました。ありがとうございます。」
図書準備室から図書室に出てきた池田勇太は、真中しずえに言ったのと同じ内容を他の五人にも簡単に伝えて職員室に戻っていった。
池田勇太がいなくなってから、「でも、まさか、真中さんの誕生日で鍵が開くとは思わなかった」と相葉由紀は真中しずえに話しかけた。
「私もびっくりしちゃった。やっぱり私って何か特別な星の下に生まれてるのかな」と冗談っぽく言うと、空木カンナは「また、そういうこといって」と笑って答えた。
「真中さんが自分の誕生日が暗証番号になってる南京錠を買ってきてつけてたって可能性はあったりする?」と、少し疲れたのか眠そうに左目をこすりながら沢木キョウが聞いてきた。
「まさか、そんなのないない」と開いた右手を左右に振りながら真中しずえが答えると、「そうだよね、僕もびっくりしちゃった」と羽加瀬信太が真中しずえに続いてそう言った。
結局、残った六人は、その後も図書準備室だけでなく図書室も見回ったが、幽霊の謎に繋がるようなものは特に何も見つけられなかった。
三十分ほど経ってから、「私、そろそろ塾にいかないといけないかも」という真中しずえが言ったので、その日の幽霊の謎を解く探検は終わった。その塾には、相葉由紀と羽加瀬信太も通っていたため、三人は一緒に学校を出て行った。
残った三人である、田中洋一・沢木キョウ・空木カンナも、途中までは一緒に帰った。その道中、田中洋一が「結局、幽霊騒ぎって何だったんだろうね」と残った二人である沢木キョウと空木カンナに聞くと、「洋一君はわからなかった?」と沢木キョウは田中洋一が想像していなかった返答をしてきた。
「え、もしかしてキョウ君は幽霊の謎が解けたの?」
「まだわからない点はあるけど、大体のことはわかったよ。」
「本当!?」
「ふふっ」と空木カンナが笑う。
「え、もしかして空木さんもわかったの?」
「それはどうかな。内緒。」
「えー、教えてよー。」
「やっぱり空木さんもわかったんだね。じゃあ、明日この三人で『犯人』に会いにいこうか。」
「犯人って・・・相葉さんを驚かせたのは、幽霊じゃなくて人間の仕業なの?」
「もちろんだよ。」
「でも、明日わかる保証はないと私は思うけどな」と空木カンナが言うと、「絶対ではないね。でも、来週には雨漏りの修理をする業者が来そうだから、明日『犯人』が現れる可能性は高いと思うよ」と沢木キョウは答えた。
「そうかもね。」
「じゃあ明日まではこのことはこの三人だけの内緒ということで。」
「え、真中さんには言わないの?」と田中洋一が聞くと、「どうする?」と沢木キョウは空木カンナの方を向いて彼女の判断を仰いだ。
「やめときましょうか。犯人のためにもね。」
「あー、やっぱりそういうことか。じゃあこの三人で行こう。僕はこの後ちょっと買い物に行ってくるよ。事件の謎を解く『鍵』を買いにね。」
「あ、そういうことね。いってらっしゃい。」
「何が何だか全然わかんないよー」と嘆く田中洋一を尻目に、沢木キョウと空木カンナはそれぞれの家へと帰っていった。
***