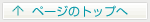SFミステリー小説:永遠の秘密
TweetSFミステリー小説:永遠の秘密
第二章:科学探偵クラブ(4)
次の日、いつもより三十分早く起きて家を出た田中洋一は、眠い目をこすりながら学校へと入った。しかし、向かったのは六年三組のクラスの教室ではなく旧校舎の図書室だった。
図書室に入ると、「遅いよ」と空木カンナが静かな声で話してきた。「ごめん。頑張って早起きしたんだけど、眠くて・・・」と答えると、「しー、誰かが近づいてくる足音がする」と沢木キョウが言って、三人は廊下から図書室へ入る出入り口からは見えない本棚の陰に静かに隠れた。
足音はどんどんと近づき、図書準備室へのドアへと一直線に進んだ。そして、南京錠を『ガチャガチャ』といじる音が聞こえてきた。すると、すぐに「あれ、おかしいな」という声が聞こえた。その声からは少し焦っている様子が感じられた。
「その鍵は今朝新しいのに替えておいたよ。ごめんね、羽加瀬君」と、沢木キョウは穏やかな声で話しかけながら羽加瀬信太に近づいていった。
「え、沢木君?どうしてここに?それに鍵を替えたって、どういうこと?」
「幽霊の正体が羽加瀬君だってことを確かめに来たんだよ。」
「僕が幽霊?何の話をしてるの?」
「うん、ちょっと誤解がある表現だったね。羽加瀬君が旧校舎の図書準備室の幽霊だと言ってるわけじゃないよ。」
「当たり前だよ。僕は幽霊なんかじゃないもん。」
それまでは突然のことに驚いている様子だった羽加瀬信太だったが、段々と少し怒ったような口調になってきた。
「怒らせるつもりはないんだよ。ごめんね。僕が言いたかったのは、相葉さんが聞いた幽霊の声と音が君によるものだったんだよねってことなんだ。」
「な、何で、そんな・・・」
「あ、それとね、ここには僕だけじゃなくて空木さんと洋一君もいるよ。」
「え・・・。」
すると田中洋一は「ごめんね。僕は羽加瀬君がここに現れるとも思ってなかったし、相葉さんの言う幽霊が君だとも知らなかったんだよ」と、本棚の陰から申し訳なさそうに出てきた。しかし、その横にいた空木カンナは「私は知ってたけどね」と独り言のように小さな声で言っていた。
「ねえ、どういう意味?僕が幽霊って何のことを言ってるの?それに、どうして鍵を替えたの?君が準備した鍵なんだから、それを僕が開けられなくてもおかしくないよね。なんで、僕が幽霊だと思うの?」と、羽加瀬信太は早口でまくしたてた。
すると、意外なことに「そうよね、証拠はないものね」と空木カンナは羽加瀬信太の味方のようなことを言った。そして、「どうなの、沢木君?」と笑みを浮かべて沢木キョウに話しかけた。
「そこで羽加瀬君の味方をするのか、空木さんは。それは読めなかったな」と沢木キョウも笑いながら答えた。
「証拠がないなら僕を幽霊だって言わないでよ。」
「まあ証拠はないんだけど、あの日、何があったかは大体わかるよ。」
「あの日って?」
「相葉さんが幽霊の声と音を聞いたあの日だよ。すごい雷と雨だった日。」
「何があったって言うの?」
「僕が思うにね、あの日、相葉さんがこの旧校舎の図書室に入ってきたとき、君はすでに隣の図書準備室にいたんじゃないかと思うんだよね。」
沢木キョウがそう言ったあと、羽加瀬信太は黙りこくったが、田中洋一はふと疑問に思ったことがあり、口を挟んだ。
「でも、図書準備室に入ってドアを閉めたら、ここの南京錠は閉められないよね。」
「うん、そうだよ。」
「いつも鍵が閉まってるドアなんだから、羽加瀬君がそのときに図書準備室にはいたってことにはならないよね。」
「そ、そうだよ。田中君の言う通りだよ」と羽加瀬信太が田中洋一に続いた。そして、「沢木君だって、昨日図書準備室に入ったよね。あの中から閉めたドアの向こう側から南京錠をかけるなんて不可能だよね。それに、図書準備室から外に出るドアはこれだけだよ」と自分の側にあるドアを指差して言った。
そして、「相葉さんが来たときも鍵がかかってたんでしょ。じゃあ、僕が図書準備室にいたわけないよ」と最後は強い口調で沢木キョウを問い詰めた。
「鍵がかかってたらね」と今度は空木カンナが口を挟んだ。
「え?」と驚いた羽加瀬信太の方を向きながら、空木カンナは「相葉さんはドアが閉まってたとは言ったけど、鍵がかかってたことは確認しなかったらしいよ。昨日言ってたよね」と言った。田中洋一は「空木さんはどちらの味方なんだろう」と思いながら、二人の会話を聞いていた。
「で、でも、相葉さんは鍵がかかってなかったとも言ってなかったよ。」
「そうね。だから真相は闇の中。証拠はないよ、って私は言ったの。でも、沢木君が考えていることは私が考えていることと同じなような気がするな。」
「考えてること?」
「うん。相葉さんが図書室に来たときには既に君が図書準備室にいた。でも、相葉さんが入ってきたことに気づかなかった君は、図書準備室の中で独り言を言いながら何かしていた。で、その独り言を聞いて、相葉さんが『誰かいるの?』って言ったんだと思うんだよね。」
「・・・。」
「それでね、静かにしてたはいいものの、雨漏りしてた天井から急に水滴が落ちてきて、首とか顔とかにあたったんじゃない?それで思わず声を出してしまった。さらに、すごい大きな雷が鳴って驚いて声を上げて動いたから、その弾みで何か近くにあるものを落とした。どう?あってる?」
羽加瀬信太は何も言わなかった。しかし、その表情は空木カンナの推理が正しかったことを認めたかのようだった。
一瞬の静寂の後、「あーあ、僕が言おうと思ったことを全部言われちゃったよ」と沢木キョウが苦笑いをしながら言った。田中洋一はそれでも羽加瀬信太が幽霊だとはまだ信じられずに、「羽加瀬君、本当なの・・・?」と聞いてきた。
しかし羽加瀬信太は「ち、違うよ。全部でたらめだよ。証拠はないんでしょ。僕じゃないよ」と、うろたえながらも自分がそこにいたことは認めなかった。
「そう、証拠はないんだよ」と沢木キョウは再び話し始めた。「でもね、昨日、このドアが開いて真中さんに続いて君が図書準備室に入ったとき、君はやけに天井を気にしてたんだよね。普通、初めて入る部屋、しかも、そこに幽霊がいるかもしれないとなれば、最初に見るべき場所は天井ではないと思うんだ。そのとき僕は、君は前にも図書準備室に入ったことがあるんじゃないかな、と思ったんだよ。でね、じゃあなんで天井を見たんだろう、と次に考えてたら、天井が雨漏りしてることがわかったんだ。それで、君は天井から水滴が落ちてくるんじゃないかと思って天井を見ていたんだな、と考えたんだ。」
「そ、そんなの君の勝手な想像だよ。」
「うん、その通り。証拠がないんだよね。でも、昨日みんなで図書準備室に入ったとき、君は奥の方のある特定の場所にばかりいたんだよね。もしかして、他の人がそこに来ないようにしてたんじゃない?しかも、その場所は雨漏りしてる場所だったよね。そこら辺を探したら何か見つかるんじゃないかな、とちょっと期待してるんだけど。」
「・・・。」
「あ、大丈夫だよ。実際にそこまで見ようとは思ってないから。」
「せ、先生にいいつけるつもり?」
「え?別に僕は先生に言うつもりは全然ないよ。空木さんは?」と沢木キョウは空木カンナに話をふった。
「そんなつもりは私にも全然ないよ。私は単に何があったか知りたかっただけだし。」
「あ、そうなんだ。僕もだよ。証拠はまだないけど、まあ、自分の考えが正しかったか間違っていたかくらいはわかったから、僕はもう満足したよ。あわよくば、もうちょっと知りたいこともあったけど、まあこのくらいで充分かなと思ってる。」
「そうね。私も同じ意見かな。」
二人の会話についていけなかった田中洋一は「え、どういうこと。これって何なの?って言うか、これからどうするの?二人とも何のためにここに来たの?それに羽加瀬君も何でここにいたの?」と、何が何だかわからないと言った様子で沢木キョウと空木カンナに聞いてきた。
「私は沢木君の推理を聞けたし、もう満足。じゃあクラスに戻るね。朝の会が始まっちゃいそうだし」と空木カンナが言うと、沢木キョウは「僕も戻ろうかな。あ、これ昨日までの鍵。その新しい鍵もあげるよ。番号は『7612』だから」と言って、ポケットから南京錠を一つ出して羽加瀬信太に渡した。
歩き始めた沢木キョウに続いて空木カンナが続いたが、二、三歩歩いたあとで空木カンナは振り返って羽加瀬信太の方を向いて、「困ってることがあったら相談に乗るよ」と言った。
旧校舎の図書室に残された田中洋一と羽加瀬信太は、しばらく図書準備室へと続くドアの近くで黙って立っていたが、ふと我にかえった田中洋一が「羽加瀬君、とりあえずクラスに戻ろう。朝の会に遅れちゃう。でも、その鍵は昨日の『0712』の方に替えておいた方がいいかも」と言い、羽加瀬信太はその通りにして二人でクラスに走って戻った。
***
その日の帰りの会が終わった後、「今日はお父さんが早く仕事から帰ってきて家族で出かけるから先に帰るね」と空木カンナに言って真中しずえは帰っていった。「うん、バイバイ」と言ってから、机の中に忘れ物がないかを確認して自分も帰ろうとして立ち上がったとき、空木カンナは羽加瀬信太に話しかけられた。
「あの、空木さん、ちょっといい?」
「うん、いいよ。図書室に行こうか。田中君と沢木君にも声かける?」
「う、うん」と羽加瀬太郎は答えて、空木カンナと一緒に田中洋一と沢木キョウのところに歩いていった。二人が近づいてくることに気づいた沢木キョウは「洋一君、じゃあ僕らも行こうか」と田中洋一に声をかけた。
「え、どこへ?」と聞いた田中洋一の質問には笑顔を返しただけで何も言わなかったが、田中洋一は三人に大人しくついていった。行き先は旧校舎の図書室。今日もやはり誰もいなかった。
「相葉さんの言ってた幽霊は僕のことだと思う。ウソをついてごめん」と泣きそうな声で羽加瀬信太は話し出した。
「でも、学校で噂になってる旧校舎の図書室の幽霊は羽加瀬君のことじゃないんだよね」と、空木カンナは質問とも決めつけともどちらとも受け取れる様子で羽加瀬信太に問いかけた。
「それは違うよ。本当なんだ。信じてって言いたいけど、今日の朝にウソを言った僕のことは信用できないよね。」
「君が噂の幽霊ってことはないだろうなと思ってるけど。」
「本当?」
「うん。それよりも私は君の話が聞きたいな。私に用があるってことは、困っていることがあって相談に乗ってほしいってことのかな?」
「・・・うん。」
そう返事をしたが、羽加瀬信太はそのままうつむいて黙ってしまった。その沈黙に耐えきれず、田中洋一が羽加瀬信太に声をかけようとした。しかし、沢木キョウが「今は何も言い出さない方がよい」という感じの視線を田中洋一に送ってきたのに気づいたので、田中洋一は話しかけるのをやめた。
空木カンナ・沢木キョウ・田中洋一の三人は、羽加瀬信太が話し始めるのを静かにじっと待っていた。
「僕、酒見君と一ノ瀬君にいじめられてるんだ」と下を向いたまま羽加瀬信太はポツポツと話し始めた。目には涙があふれそうになっている。
「最近はあっちの図書室にある漫画をこっそり盗んで持ってこいって言われてるんだ。」
「だから時々、図書室から漫画がなくなってるって不満がみんなから出てきてるんだね」と、田中洋一は思わず口を出してしまった。
「・・・うん。受付カウンターで貸し出しの手続きをしないでこっそり持ち出してたから、そういうのは行方不明扱いの本になってると思う。僕だってしたくなかったけど、あの二人にいじめられるのが怖くて仕方なかったんだ・・・。」
「なるほど。で、その漫画をこの図書室の隣の図書準備室に隠してたってわけなのね。」
「うん。家に持って帰っても隠しておくスペースはないし、親に見つかってほしくもないから・・・。」
「木を隠すなら森の中、ってことね。で、これからどうするの?」
「わからない。空木さんたちは先生にも言うよね。きっと親にも知られる。覚悟はしてるけど、怒られるのは怖いよ。それに、きっと酒見君や一ノ瀬君にももっといじめられるようになると思う。もう学校に来たくない。」
羽加瀬信太の目からは涙が溢れ出てきてる。その姿を見て田中洋一は少し焦り出す。しかし、空木カンナは「そっか。ところで質問なんだけど、前の南京錠の『0123』の番号はどうやって調べたの?」と、泣いている羽加瀬信太の様子には気にも留めずに質問を続けた。「うん、そうだね。僕もそれは気になってた」と沢木キョウも続けた。
「え、ちょっと待って空木さん。沢木君も。羽加瀬君がかわいそうだよ」と田中洋一が口を挟むと、テーブルの上にポタポタと落ちてくるくらいに羽加瀬信太の涙の量は多くなった。田中洋一は急いでポケットからティッシュを取り出そうとしたが、それよりも早く空木カンナがハンカチを羽加瀬信太に手渡した。「ありがとう」と小さい声で答えて、羽加瀬信太はそのハンカチで受け取り涙を拭った。
「田中君もありがとう。でも大丈夫だよ。最後まで説明するね。前の南京錠を開けられたのは偶然なんだ。」
涙声のまま羽加瀬信太は続ける。「五年生のときくらいから、時々ここにきて『0000』から順に番号を合わせていったんだ。学習塾に行く日に、ときどきここで宿題をやってることがあったんだけど、ふとあの図書準備室に何があるのか気になって・・・。宿題が早く終わった日とかに試してたんだ。」
「『0000』から124回試したってこと?」と、沢木キョウが聞いた。
「うん。まさか本当に開くとは思わなかったんだけどね。」
「すごいね。地道に根気よく継続して努力できるのは君の長所だね」と空木カンナが言うと、突然の褒め言葉に羽加瀬信太は少し戸惑ったようで、何とも言えない表情をした。
「新しい鍵に替えた理由は?漫画を隠しているのを見つけられたくなかったから?」と沢木キョウが続けて質問した。「うん・・・」と再びうつむき小さな声で答えた。「なるほど。で、昨日、ここを掃除するということを聞いてびっくりして、その掃除に参加することにしたのか」と、隣の図書準備室を見ながら、まるで独り言のように沢木キョウはつぶやいた。
「これで幽霊の謎は全て解けたってことかな」と、空木カンナが言ってから、一呼吸ついて、「それで、さっきの質問だけど君はこれからどうするの?」と羽加瀬信太に問いかけた。
羽加瀬信太は下を向いたまま、「わからない。僕はどうすればいいと思う?」と消え入りそうな小さな声で逆に聞いてきた。
「う〜ん、それは君次第なんだよね。相談には乗るし、助けてあげたいなとも思うけど、君がどうしたいか決めないと先に進めないと思うよ、私は。沢木君や田中君はどう思う?」
「洋一君から先にどうぞ」と、突然話を振られた田中洋一は「え?」とびっくりしたが、少し考えて「先生に言って酒見君や一ノ瀬君に羽加瀬君へのいじめをやめるように頼もうよ」と言った。
しかし、空木カンナは田中洋一の意見に同意することなく、「酒見君や一ノ瀬君が羽加瀬君に漫画を盗んで図書準備室に隠しておけって言ったという証拠はあるの?」と、逆に聞いてきた。
「え?」と、思わぬ質問に、田中洋一は少し驚いてそう言うと、「そこをはっきりしておかないと、きっと二人はそんなことは言ってないっていうと思うんだよね。そうしたら、羽加瀬君が一人で漫画を新校舎の図書室から盗んで、ここの隣の図書準備室に隠してたってことになるよ」と、空木カンナは自分の考えをそう述べた。
「え、そんな。羽加瀬君がそんなことするわけないよ。先生だってきっと信じてくれるよ。羽加瀬君はいつも真面目に勉強してるんだよ。でも、あの二人はそうじゃないんだし。」
「証拠はないけど、悪ガキは悪いことをしてるに違いないし、優等生はそんなことをするわけがないって言いたいのかな?」と、少しからかうような口調で空木カンナが田中洋一に質問した。
「そ、そんなつもりはないよ。でも・・・」と田中洋一が言葉につまっていると、それまで黙っていた羽加瀬信太が意を決したように「酒見君と一ノ瀬君に、彼らの言いなりにはならないと言ってくる。そして、漫画も元の場所に戻すし、先生にも全部を説明して怒られてくる」と言った。
「え、そんなの大変だよ」と田中洋一が言ったが、「ありがとう。でも大丈夫。元はと言えば、最初から僕がノーと言えばよかったんだもん。それに、実際に漫画を盗ったのも、勝手に隣の部屋に入ったのも僕なんだし。きちんと責任をとらないといけないと思う。」と力強く返した。
「殴られたり蹴られたりするかもよ。それでも大丈夫?」と空木カンナは聞いたが、「怖いけど、今のままの状態が続く方がずっと怖い」と少しだけ震える声で羽加瀬信太は答えた。
「偉いね。頑張って。でも、先生には別に言わなくてもいいと思うよ」と言うと、沢木キョウも「僕もその意見に賛成」と付け加えた。
「うん、あの二人が羽加瀬君にしてたことを気づけなかった先生にきちんと説明する必要はないよね。あ、もしあの二人がもし暴力を振るってきたり、いじめを続けるようだったら、また私たちに相談して。全員で立ち向かえば怖くないわよ。ね、沢木君に田中君。」 「そうだね。一ノ瀬君が体が大きいって言っても、所詮は日本人の小学六年生だし。それに酒見君にいたってはごくごく普通の体格だもんね。アメリカでは、もっと大きなクラスメートや乱暴なクラスメートとも一緒にいたから、全然問題ないよ。あのくらいの力なら、一回や二回くらい殴られても平気だと思うし、そもそもあのタイプって自分たちの方が少数派ってなったら急に大人しくなるよ。みんなでいけばきっと大丈夫。」
「え、僕は痛いのは嫌だし怖いんだけど・・・」と田中洋一が言うと、これまで泣き顔だった羽加瀬信太の顔に笑顔が戻り、「大丈夫、そんなことにはならないようにするよ」と言った。そして、「みんなに相談してよかった。本当にありがとう」と続けた。
***
空木カンナら四人は、その後でみんなで図書準備室に入り、羽加瀬信太が隠していた漫画本を回収して、こっそりと新校舎の図書室に戻した。
帰り道、四人は途中までは一緒に帰ったが、一番始めに空木カンナがみんなと別れた。別れ際、空木カンナが「羽加瀬君、何かあったらいつでも私たちに相談してね」と言うと、羽加瀬信太は「うん、ありがとう」と、これまで抱えていた悩みがなくなって気持ちが軽くなったのか、明るい声でそう言った。
その後、五分ほど残った三人で歩いてから、羽加瀬信太が「じゃあ、僕はこっちだから。今日は本当にありがとう」と言ってから、田中洋一と沢木キョウに「バイバイ」と手を振って自分の家の方へと帰っていった。
羽加瀬信太の姿が遠くに去っていって、二人で再び歩き始めたところで田中洋一が沢木キョウに話しかけた。
「どうなることかと思ったけど、何とかなりそうでよかった。」
「まあ、羽加瀬君の問題はまだ解決してないけどね。」
「うん、そうなんだよね。心配だけど、きっと大丈夫だよね。」
「大丈夫だと思うよ。羽加瀬君が強く出れば、酒見君と一ノ瀬君はこれ以上は意地悪をしなくなるんじゃないかな。今日の様子を見ると、羽加瀬君の決心は強いようだし、彼なら大丈夫。何かあったら一緒に助けてあげようね。」
「う、うん・・・」と少し不安そうに田中洋一は答えた。
「大丈夫大丈夫、そんなに心配しなくても。そのときは空木さんも一緒だし、きっと真中さんも味方になってくれるはず。それだけの人数がいれば、彼らも強く出れないよ。それに・・・」
「それに?」
「空木さんがいるだけで色んな問題ごとは解決しそうな気がするんだよね。彼女は本当に六年生なの?なんか大人と話しているような感じがするんだけど。」
「うーん、実は僕もそんなに空木さんのことは知らないんだよね。彼女、五年生のときに引っ越してきて、クラスでは静かにしてたから。でも、確かに、今日の空木さんは、まるで大人が喋っているようだったね。」
そのとき、田中洋一がふと何かを思い出した。
「あ、そうだ。僕、まだ一つ疑問があったんだ。」
「何?」
「羽加瀬君が持ってきた新しい鍵、番号は『0712』だったでしょ。で、真中さんの誕生日も七月十二日だったでしょ。すごい偶然だよね。あのとき、もし真中さんの誕生日が違っていて、あの場にいたみんなの誕生日が七月十二日じゃなかったら鍵の番号はわからないままだったよね。その場合、羽加瀬君はどうしてたんだろ。」
「あれ、偶然じゃないと思うよ。」
「え?」
「羽加瀬君は真中さんの誕生日が七月十二日だったって知ってたんだよ。で、その番号の鍵は前から持ってたんじゃないかな。だから、その鍵を家から持ってきて付け替えたんだと思うよ。」
「なんで?」
「それは、何でそんなことしたのかって質問?それとも何で知ってるのって質問?」
「えっと・・・両方・・・かな?」
「空木さんがここにいたら『証拠はないんだよね』って言われそうだけど、僕が思うに羽加瀬君は・・・。いや、それは僕の口からは言わない方がいいかな。」
「えー、そこまで言って内緒なの?」
「そういう人の気持ちがわかるようになるのも良いマジシャンの条件だと思うよ。頑張って練習しないと。じゃあまた来週の月曜日に会おうね。バイバイ。」
そう言って沢木キョウは去っていった。後に残された田中洋一は、呆然として沢木キョウの後ろ姿を見続けていた。
(「第二章:科学探偵クラブ」おわり)