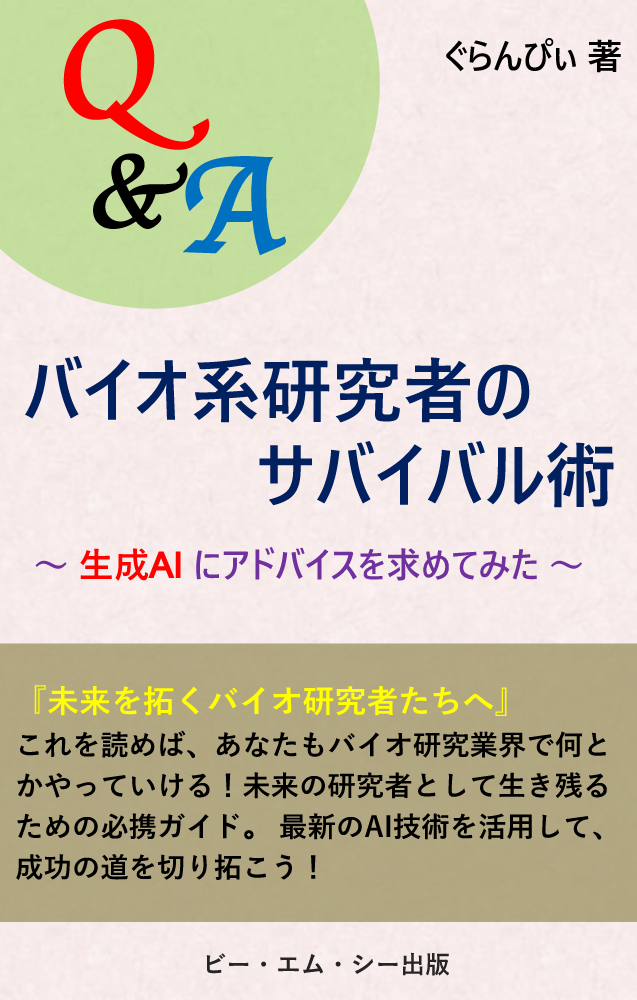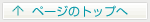生成AIが書いたバイオ系短編小説集
Tweet生成AIが書いたバイオ系短編小説集
夢
大学院生の中山は、夜遅くまで研究室にこもっていた。バイオ系の研究に没頭する彼は、マウスの遺伝子操作を専門にしていた。机の上には、シャーレやピペットが散乱し、冷蔵庫には無数のサンプルが眠っている。時計の針は深夜2時を回っていたが、彼はまだ論文のデータをまとめていた。
その夜、中山は疲れ果てて机に突っ伏した。すると、奇妙な夢を見た。自分が小さな檻の中にいる。体は小さく、白い毛に覆われ、長い尻尾がピクピクと動く。マウスだ。檻の外からは巨大な影が近づき、白衣を着た誰かが冷たい金属の器具を持っている。中山は逃げようとしたが、足は短く、力は弱い。金属のピンセットが彼をつまみ上げ、注射器が近づく。針が皮膚を刺す瞬間、彼は恐怖で目を覚ました。
「夢か……」
中山は額の汗を拭った。心臓がドクドクと鳴っている。研究室の蛍光灯がチカチカと点滅し、静寂が耳に響く。時計を見ると、3時を少し過ぎていた。彼は水を飲んで落ち着こうとしたが、夢の感触がリアルすぎて気持ちが悪かった。
翌朝、中山はいつものように研究室へ向かった。教授や仲間たちは忙しく動き回り、マウスのケージをチェックしている。中山も自分の実験マウスを確認しに行った。ケージの中の白いマウスが、彼をじっと見つめている気がした。
「お前、昨日の夢に出てきたな」
彼は冗談めかして呟いたが、マウスはただ赤い目でこちらを見ているだけだった。
その日から、中山の日常に小さな異変が現れ始めた。まず、食事が妙に味気なく感じるようになった。いつも楽しみにしていたコンビニの弁当が、ただの固形物にしか思えない。次に、体が軽くなった気がした。階段を上るのが楽で、疲れにくい。しかし、同時に何か違和感があった。鏡を見ると、顔が少し痩せているように見えたが、研究のストレスだろうと自分を納得させた。
ある夜、中山はまた夢を見た。今度はもっと鮮明だった。自分がマウスとして檻の中にいる。白衣の人間が彼を観察し、メモを取っている。中山は叫ぼうとしたが、声は出ず、ただ小さな鳴き声が漏れるだけだ。白衣の人物が近づき、彼の体に何かを注射した。すると、体が熱くなり、意識が遠のく。そしてまた目が覚めた。
「またか……」
中山はベッドで息を整えた。時計は4時。外はまだ暗い。彼は起き上がり、水を飲もうとしたが、手が震えていることに気づいた。いや、手だけではない。全身が震えていた。鏡を見ると、目が少し赤みを帯びているように見えた。錯覚だろうか。
「寝不足だ。少し休もう」
彼はそう呟いて、再び布団にもぐった。
翌日、研究室で異変がさらに進んだ。中山がマウスのケージを開けると、マウスたちが一斉に彼の方を向いた。普段なら餌を求めて動き回るだけなのに、今日は全員がじっと彼を見つめている。赤い目が、まるで何かを訴えるように光っている。中山はぞっとした。
「気持ち悪いな……」
彼はケージを閉め、実験ノートに目を移した。しかし、文字がぼやけて見える。眼鏡をかけ直しても変わらない。疲れ目だろうか。それとも――。
その夜、中山は研究室に残ってデータを整理していた。教授が帰り、他の学生もいなくなった。静まり返った部屋で、彼はふと手を止めた。背後に気配を感じたのだ。振り返ると誰もいない。ただ、マウスのケージが並ぶ棚があるだけだ。しかし、気配は消えない。むしろ近づいてくる。
「誰かいるのか?」
声に出してみたが、返事はない。代わりに、ケージの中から小さな音が聞こえた。マウスたちが一斉に動き始めたのだ。ガリガリと爪で檻をかく音、ピーピーと鳴く声。中山は立ち上がり、棚に近づいた。すると、マウスたちが全員こちらを向いている。赤い目が暗闇で光り、彼を凝視している。
「何だ、これは……」
中山は後ずさりした。だが、その瞬間、足がもつれて転んだ。床に倒れた彼を見下ろすように、マウスたちの目がさらに輝いた。
翌朝、中山は研究室に来なかった。教授は不思議に思ったが、彼が風邪でも引いたのだろうと気にしなかった。しかし、昼過ぎに中山の机の上に奇妙なメモが見つかった。殴り書きのような文字で、こう書かれていた。
「俺は見られている。赤い目で。」
教授は首をかしげたが、忙しさにかまけてそのままにした。
数日後、中山は研究室に戻ってきた。だが、様子がおかしかった。目はうつろで、口数は少なく、時折小さな震えが体を走らせている。教授が声をかけると、彼はぎこちなく笑った。
「大丈夫です。ただ、ちょっと疲れてただけです」
そう言って、彼はマウスのケージに向かった。だが、その手つきはどこかぎこちなく、まるで自分が何をすべきか忘れたかのようだった。
その夜、中山は再び夢を見た。今度は自分が完全にマウスだった。檻の中で震えながら、白衣の人物を見上げる。顔は見えないが、その手には注射器がある。中山は逃げようとしたが、体は動かない。注射器が近づき、針が刺さる。そして――目が覚めた。
翌朝、研究室に中山の姿はなかった。机の上には、またメモが残されていた。
「俺はもう人間じゃないかもしれない。」
教授はそれを読んで眉をひそめた。冗談にしては不気味すぎる。中山の自宅に電話をかけたが、誰も出なかった。心配した教授は、彼のアパートを訪ねることにした。
アパートのドアは開いていた。中に入ると、部屋は散乱し、壁には爪で引っかいたような跡が無数にあった。台所には食べ物のカスが散らばり、まるで動物が荒らしたようだ。そして、ベッドの上に中山がいた。いや、中山だったものだ。彼の体は異様に小さく、白い毛に覆われ、長い尻尾が垂れ下がっていた。目は赤く光り、教授を見上げて小さく鳴いた。
「中山君……?」
教授が声をかけると、それはピーピーと鳴きながら逃げ出した。小さな体はベッドの下に隠れ、二度と出てこなかった。
研究室に戻った教授は、中山のデータを確認した。彼が最後に扱っていたのは、遺伝子操作用のウイルスだった。マウスに注入し、特定の形質を変える実験だ。だが、記録には不思議な点があった。サンプルが一つ足りない。教授は冷や汗をかいた。もし中山が誤って自分にそれを――。
その日から、研究室では奇妙な噂が広がった。夜になると、小さな足音が聞こえる。赤い目が暗闇で光る。誰かがケージを覗くと、そこには見慣れないマウスが一匹増えている。そして、ある日、教授は決定的なものを見つけた。中山の机の引き出しに、小さな白いマウスが隠れていたのだ。目は赤く、じっと教授を見つめている。
「中山君……なのか?」
教授が呟くと、マウスは小さく鳴いた。そして、次の瞬間、ケージの中へと連れていかれた。
中山の名は研究室から消えた。だが、マウスの数はなぜか減らない。いや、むしろ増えているようにさえ見える。教授は気づいていた。新しい実験が始まるたび、白衣を着た自分が、マウスを ―いや、中山を― 実験動物にしていることを。そして、その赤い目は、いつもこちらを見つめているのだ。