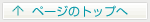研究者の声:オピニオン
Tweet2016年11月29日更新
学術論文の査読システムが崩壊の危機に瀕している
査読(英語ではPeer-Review)とは、同分野の研究者が他者の研究内容を評価することを示します。研究活動をする上で、ほとんどの研究者は自身の研究成果を発表する前段階の論文査読は避けては通れません。論文の査読は、研究成果が世に出る前にその内容が科学的に正しいかどうかを判断する目的で使われており、科学分野にとって必要不可欠なシステムです。
しかしここ数年、特にバイオ系の学術雑誌に投稿された論文の査読プロセスが、非常に好ましくない状況に陥っています。好ましくない状況というのは「投稿された論文が同分野の研究者によりその研究内容を科学的に評価される」という査読システムの根本が崩壊寸前であるということです。
何故そのようなことが起きてしまったのでしょうか。1番の原因は、現在の査読プロセスに種々の問題が含まれていることが挙げられます。そこで本オピニオン記事では、論文の査読プロセスを一つずつ振り返り、そこにある問題点を見ていきたいと思います。
***
1. 雑誌の編集部による論文チェック
投稿された論文は、まず雑誌の編集部によってチェックされます。基本的にここでは、論文の科学的な内容に関するチェックは行われません。論文の体裁が整っているか、必要な書類は提出されているか、動物実験はきちんと認可された条件で行われているか、などがチェックされます。雑誌によっても異なりますが、この段階は1週間以内に終わることが多いです。この段階では、査読システムを崩壊させるような大きな問題はあまり見当たりません。
2. 担当編集者による論文チェック
編集部の事前チェックが行われた後、投稿された論文は科学的な側面から評価されることになります。この段階ではまず、投稿された論文の査読プロセスを担当する「編集者(英語ではHandling Editorと言われることが多い)」が決まります。一般にその編集者は、同分野の研究者かつ各学術誌の編集委員会(Editorial Board)の中から選ばれます。
担当編集者の役割は多岐に渡ります。1つの大きな役割は、投稿された論文を査読する研究者(査読者:英語では単にReviewerまたはRefereeと言われることが多い)を2~3名選んで論文の評価を依頼することです。しかし、投稿論文の内容や質がその学術誌と合わない場合は、担当編集者の判断で、査読候補者に論文査読を依頼する前にReject(掲載を却下)となることがあります。
この段階(雑誌の編集部のチェックが終わり担当編集者が決まるまで)は一般には2~3日程度で終わるのですが、一部の学術誌では担当編集者が決まるまでに1ヶ月以上かかる場合もあります。また、担当編集者によっては自分に割り当てられた投稿論文を読まずに放置し、1ヶ月以上してから査読者探しを始める場合もあります(酷い場合にはそのまま放置して、数カ月が経過してから雑誌の編集部が新たに担当編集者を選びなおすこともある)。
何故そのようなことが生じてしまうのでしょうか。1つには、各学術誌の編集委員会は基本的には無償のボランティアであるということが挙げられます。そのため、投稿論文数が増えて編集委員の負担が大きくなっている現在、無償のボランティアである編集委員が割り当てられた全ての投稿論文の査読プロセスを迅速に行うことは期待できなくなっています。
また、学術誌の絶対数が増えたことから、担当編集者となりうる編集委員の絶対数も増えてきました。1人の研究者が複数の学術誌の編集委員となることは可能ですが、それでも限界はあります。そのため、一昔前ならば編集委員(=投稿論文の担当編集者)になるにはまだ経験が足りないとされた研究者でも投稿された論文の査読プロセスを任されることとなっています。当然のように、そのような人々は担当編集者として質も低く責任感も薄い傾向にあるので、査読プロセスには種々の問題が生じてしまいます(以下で詳しく解説します)。
3. 査読者による論文チェック
この段階がいわゆる「査読(Peer-Review)」となります。査読期間は雑誌により異なりますが、一般に査読者は10日~3週間で査読結果を返送することを求められます。しかし、ここにはいくつもの問題があります。
1つは適切な査読者が見つかりにくくなっているということです。通常、1つの投稿論文は2~3名の査読者によって科学的に評価されます。しかし、科学技術が進歩し専門分野の細分化が進んだことで、その投稿論文全体を1人の研究者が科学的に評価するのが難しくなりました。というのも、まとまった研究になればなるほど異なる専門分野を持った複数の研究グループが共同で論文を書くことになるからです。
また、投稿論文の絶対数が増加したことも、査読者を見つけることを困難にしています。論文査読を科学的・客観的に行える能力を持った研究者は、職位が上位であり非常に多忙です。そのような人は、余程の理由がない限りは論文査読を受けないことが一般的となってきています。現在はAssistant Professorクラスの研究者であっても、査読依頼のメールは引っ切りなしに届き、1日に3通の査読依頼メールが来たということも決して珍しいことではありません。そして、当然のようにそのような査読依頼は断られ(時にはスルーされ)、その都度、査読者が決まるまでの時間が延長されます。運が悪いと、査読者が決まらないまま数ヶ月が経過したという事態にも陥ります。
そのため昨今では、査読者候補として学生・ポスドクを含む駆け出しの研究者も含まれるようになってきています。そして、当然ですが、そういう人からの査読コメントは的外れなことが多いです。私が聞いた査読コメントの中には「著者たちの頑張りが認められるから今後に期待してアクセプト」という耳を疑うようなものもありました。(この点は後ほど詳しく論じます)
さて、無事に査読者が決まったとしても、「締め切り」に間に合うように査読コメントを返送してくる査読者は多数派ではありません。特に論文査読のシステムの実情・内情に詳しい研究者であれば、締め切りを平気でブッチします。
私が聞いた範囲での情報から推察するに、査読の締め切りが2週間であった場合、およそ半数は締め切りに間に合わせることはありません。締め切りに間に合わせなかった人のさらに半数(全体の25%)はその後2週間が経過してもコメントを出さず、さらにその半分(全体の10%くらい)は編集部からの度重なる催促メールにも動じず、そのまま音信不通になることすらあります。
なぜそんなことがまかり通るのか不思議に思う方もいるかもしれませんが、そこには色々な事情があります。1つは、査読者も編集委員同様に無償のボランティアであるということが挙げられます。そのため査読者は他にもっと重要な仕事(研究者は大抵はいつも忙しい)があれば、そちらを優先します。しかも雑誌の編集部は、無料で仕事を発注しているということから査読者には強い態度を取れません。
さらに、査読者の個人情報は論文の著者には明らかにはされませんので、仮に査読者が不誠実な対応をしていたとしても、著者から査読者への報復がなされることはありません。もちろん編集委員は、自分が依頼した査読者が誠実か不誠実かはわかります。しかし、査読者の側は誰が編集委員か事前にわかるので、その編集委員が自分の研究活動に影響を与えうるようなキーパーソンであった場合は誠実な対応をします。逆に言えば、そうでない場合は仮に自分が不誠実な対応をしたからといって、その編集委員から何かをされる心配はないということを理解しています。(編集委員も雑誌が変われば単なる1人の査読者になりうるので、こういうのはある意味でお互い様だと少なくない数の編集委員が思っているようです)
また、査読コメントの内容そのものにも問題な点があります。非常に残念なことに査読コメントの質は年々低下していっています。先ほども述べましたが、一昔前なら査読者にならない(なれない)ような研究者までもが査読者となっています。しかも、一昔前なら博士号を取得できなかった人(もしくは博士課程に進まなかった人)が博士号を取得して研究者となっているため、現在の査読者のレベルは目を覆うほどに酷い状態です。先にお示ししたコメント以外にも、たくさんの酷いコメント例を筆者は聞いてきました。中には査読コメントというより「感想文」と言うべきものもあります。本記事をお読みの方の中にも「この査読者は自分にどう原稿をリバイスしてほしいのだろうか?」というような疑問を思った経験のある方も多いのではないでしょうか。
4. 投稿論文の掲載の可否
さて、査読プロセスの続きです。必要数の査読コメントが揃ったあとは、担当編集者が査読コメントの内容に応じて投稿論文の雑誌掲載の可否を決定します。通常はrevise(このままでは掲載できないが必要な改訂が行われれば掲載できる)かreject(掲載の拒否)となります。(この業界の通例で、余程のことがない限りは、改訂なしでのAccept(掲載を許可)とはなりません)
さて、先に査読者のレベルが低下しているということを述べましたが、レベルが低下しているのは何も査読者だけではありません。学術誌の絶対数が増えたことにより編集委員の数も増えたため、こちらの質の低下も顕著です。
例えば、編集委員の中には担当した投稿論文に目を通すことなく、論文タイトルと論文キーワードだけから適当に査読者を選びます。そして、査読者のコメント内容にすら目を通さずに、査読者が選択したaccept/revision/rejectの項目だけを見て掲載の可否を決定する人もいます。
そのため、査読コメントとして不適なコメントが何のチェックもされないまま著者に送られることになります。また、査読コメントの中には非現実的な追加実験の要求もありますが、それを非現実的だと著者達が反論しても、意地悪な査読者や原稿・査読コメントを精査していないやる気のない編集委員はまともに取り合ってくれません。
そのような状況のため、著者(主にCorresponding AuthorとなるラボのPI)は自分の論文をアクセプトさせるため、何とかして査読コメントに対応しようとし、それは現場で働くポスドク・学生への無言のプレッシャーとなり捏造の温床にもなりえます。
査読コメントが科学的な正当性を担保できなくなるもう1つの大きな理由があります。それは、査読者が論文著者の研究のライバルとなりうることが往々にしてあるということです。
本来であれば(理想を言えば)、同じ分野の研究者同士は、お互いに切磋琢磨し必要なときにはサポートしあうべきです。ライバルの研究への批判は、科学的な根拠に基づいて行うべきであり、個人の感情に起因する批判は科学者としてやってはいけない行為です。
しかし、アカデミアのバイオ業界がレッドオーシャン化してしまった現在、各々の研究者にそれだけの余裕はありません。「殺らなければ殺られる」や「正直者はバカを見る」がまかりとおり、自分が査読する論文に対しては出来るだけ厳しいコメントをして(さらに査読プロセスを長引かせ)相手の研究を妨害してやろうという研究者が珍しくなくなってきました。そして、非常に残念ですが、ずる賢く出世していっている研究者は、自分をナイスに見せたまま他人の投稿論文に一見正当なケチをつける技術が高いです。
***
以上のように、今や学術論文の査読プロセスは至るところで問題だらけで、「査読(Peer-Review)の意義」はもはや見る影も形もありません。論文発表は、ある意味で全ての研究者に求められる重要な役割の一つです。たくさんのお金を使って実験をしても、それが世にでなければ意味がありません。
しかし、今の査読プロセスでは、論文を世に出すためには、科学的でないコメントを長期間にわたり待つ必要があります。それは、科学技術のスピーディーかつ意義のある発展を阻害するものとも言えます。
そもそも査読プロセスは、研究者の「善意」「正しいプライド」「正当な資質」に依存したシステムであり、少数の研究者が狭い範囲の仲間内で楽しくノンビリと研究をやっていた時代の名残なのかもしれません。
しかし時代は変わり、研究者としての「性善説」に基づいたシステムは現在では当然成り立つはずもなく、査読システムはもはや崩壊寸前です。しかも、その「査読システム」を忙しい研究者に無報酬で発注している学術誌は、Peer-Review Journalであるという看板を掲げ金儲けに邁進しています。果たして今の学術誌は、科学的に信頼に足る学術論文を世に送り出せているのでしょうか。
***
ではどうすれば「査読システム」を効果的なものへと生まれ変わらせられるのでしょうか?残念ながら、それは私のような一介のサイエンス・ライターがどうこうできる問題ではなさそうです。研究業界全てを巻き込んだ一大論争が必要となるでしょう。
この文章が、病んだ査読システムおよび研究業界を治療するための一助となれば幸いです。
執筆者:樋口恭介(サイエンスライター)
樋口恭介(サイエンスライター) 氏推薦の書籍です