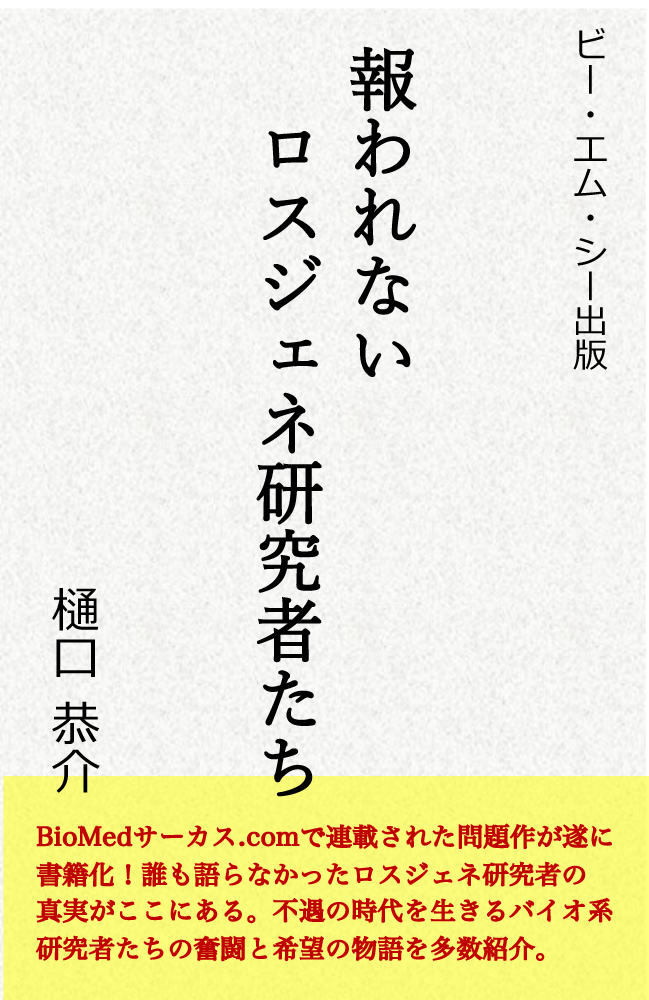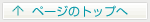研究者の声:オピニオン
Tweet2025年3月10日更新
特任助教の現実〜バイオ研究の厳しさとシステムへの疑問
3年間務めた特任助教の契約が終了する。いわゆる「雇い止め」だ。大学に「更新ができないか」「なんとか仕事を続けられないか」などと何度か尋ねたが、「規則ですので」の一点張りだった。3年間、朝から晩まで雑用込みでラボにこもり、自分の時間もまともに持てないような生活を送ってきた結果がこれかと、虚しい気持ちでいっぱいだ。
私はバイオ系の研究者である。蛋白質解析を専門としていて、培養細胞を使って実験をしてデータを集めてきた。大学院生の頃は、研究を通じて何か大きな発見を成し遂げたいという夢があった。特任助教になったばかりの頃は、その夢に向けて論文を大量生産しようと思っていたが、色々な雑用に追われて研究に使える時間は多く見積もってもラボにいる間の20~30%しかなかった。
現実は甘くはなかった。雑用の合間を縫ってトライした実験はうまくいくことの方が圧倒的に少なかった。ラボの教授は厳しいことを言うタイプではなかったが、彼からは常に「もっと結果を出せ」というプレッシャーをかけられていたように感じていつもストレスだった。任期の終わりが見えてきた頃に、ようやく論文を仕上げ投稿できた。だが、インパクトファクターは3くらいの中堅どころの雑誌で、仮にその論文が出たからといって次のポストが保証されるわけでは全然ない。そして結局、雇い止めだ。研究者として生きていくって、こんなにも不安定なのかと痛感している。
***
特任助教のポジションは、3~5年の契約が基本だ。若手研究者に経験を積ませるための「ステップ」だと、この業界の偉い人たちは言うけれど実態は違う。契約が終わればそれで終わり。次のポストが用意される保証はないし、任期終了後にどうなるかは自分次第、いや、運次第と言ったほうが正しいかもしれない。私はこの3年間、必死に働いた。だが結局、今の大学では職を続けることはできなかった。理不尽にもほどがある。
私の前の先輩も、同じように雇い止めを経験した。その人は今、民間企業で働いているらしいけど、研究からは離れてしまった。研究職のポジションが民間企業でも見つからなかったかららしい。私もその道を辿るのかと思うと、少し寂しい気持ちになる。せっかく博士号まで取って、研究者としてのキャリアを築こうとしたのに、こんな形で終わるなんて想像もしていなかった。
***
バイオ系の研究は、とにかくコストがかかる。
試薬一つが高額で、実験装置の維持費も馬鹿にならない。私の所属していたラボでは、顕微鏡のメンテナンスだけで年間100万円以上かかっていた。それなのに、国や大学からの研究費は年々減っている。
教授からは「君も早く自分の科研費が取れるといいね」と言われるけど、特任助教のポジションではそもそもトライできる研究費のプログラムは少ないし、その採択率も悲しくなるくらい低い。採択率が10%ということも珍しくない。10人に1人しか通らないなんて、ほとんど運任せのギャンブルだ。審査員がきちんと審査できているとも思えない。それでも、研究を続けるためには申請書を書き続けなきゃいけない。時間も労力も奪われるばかりだ。
さらに、バイオ研究は成果を出すのに時間がかかる。細胞を育てるのに数週間、実験が失敗すればまた一からやり直し。私は2年ちょっとかけて論文を仕上げたけど、自分の論文を投稿する直前に海外から似たような論文が出されてしまった。その論文をオンラインで見たときは、乾いた笑いしか出なかった。それまでの努力が、既報論文の「裏付け」にしかならなくなったからだ。
***
任期の終わりの数ヶ月前に教授にも自分の将来のことを相談した。しかし、「君には悪いけど、うちのラボも予算が厳しくてね。研究員を雇う余裕はないんだよね」と半笑いで言われた。一人の人間の人生を真剣に考えている様子はなかった。
私たち若手がデータを出し、論文を書いて、その成果は教授の業績になるというのに、その若手の人生のことは大して考えてくれない。私は3年間、自分のプロジェクト以外にも、このラボのために働いてきた。それなのに、こんな扱いしかしてもらえないのかと悔しくて仕方なかった。
教授は他所では人格者で通っており、講演なども頻繁に行なっている。しかし、ラボの運営に関しては無責任だと感じることが多かった。予算管理は杜撰で、若手のキャリア支援に力を入れる様子もない。
「次のポストはどうしたらいいですか」と聞いても、「民間企業に行くか、海外のラボを探してみるかだね」と曖昧な答えしか返ってこなかった。研究に関しても、それほど意味のある指導は受けてこなかったようにも思う。そんな教授には、今は悲しいを通り越して呆れた気持ちしか持っていない。
雇い止め後の選択肢は限られている。大学でのきちんとした正規のポストは、特任助教をした人ではほぼみつけられない。だから、ポスドクの身分に戻り別のラボに移るか、民間企業に就職するかが主な選択肢だ。でも、どちらも簡単じゃない。ポスドクは給料が低く、契約も短期間で、また不安定な立場が続く。私はもう30歳半ばになる。いつまでもそんな生活を続ける気力も体力もない。
民間企業への就職も考えてみたけど、バイオ系の求人は少ない。そもそも民間企業は「雇い止め」された特任助教あがりの人は雇いたがらない。社会経験がないからだ、という理由を聞いたこともあるが、日本はまだまだ新卒採用が好きなんだろう。実際に製薬企業に応募したのだが、論文数が少ないと思われたのか、面接で「うちはスピード感を重視してる」と言われてしまった。その時は、正直、返す言葉がなかった。これまで積み上げてきたスキルや経験は、企業にとっては価値がないってことなのかと、やりきれなかった。
***
かつて、私は研究に夢を見ていた。白衣を着て、新しい発見を追い求める姿に憧れた。でも、現実は厳しい。データに追われ、教授の言うことを聞いて、雑用をしながら実験や申請書を書く毎日。そして期限が来たらサヨナラ。これが研究者の人生なら、過去に戻って研究に夢を抱いていた自分を叱責したい。
周囲を見ると、大学に残らなかった同世代は安定した仕事に就き、家庭を築いている。私には貯金も少なく、将来の計画も立てられない。もちろん結婚もできない。両親には「博士まで取ったのに、どうするの?」と心配されるけど、私だってどうしたらいいのか分からない。研究を続けたかっただけなのに、こんな状況に追い込まれるなんて納得がいかない。
日本の大学研究のシステムには、根本的な問題があると思う。特任だ、ポスドクだと名前を変えて、不安定な雇用を増やしているだけだ。国は「科学技術を推進する」と言いながら、研究現場の実態はこんなものだ。誰かがこの仕組みを変えてくれない限り、私のような雇い止めを経験する研究者は増え続けるだろう。
でも、正直、変わる気配はない。上層部は「予算がない」で逃げ、国は「頑張って」と言うだけ。結局、潰れるのは私たち末端の研究者だ。こんな状況で、どうやって研究を続けろというのか。
***
ここ最近はラボに行くたびに寂しさが募る。実験ノートを整理し、試薬を片付け、デスクを明け渡す準備をしていると、ここでの3年間の思い出が消えていくようだ。ここで過ごした時間は、私にとって大切なもののはずなのに、それは何も残らないんだなと実感した。
今は、次の道を探している。民間企業で働くか、海外のラボに移るか、まだ決められない。でも、研究への情熱は薄れつつある。バイオ研究者としての道を、もう一度歩みたいとは今は思えない。そんな気持ちで、この文章を終えたいと思う。
著者:末は無職かホームレスか