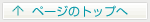SFミステリー小説:永遠の秘密
TweetSFミステリー小説:永遠の秘密
エピローグ
小学校の卒業式の日、校門のところで、真中しずえと最後の挨拶を交わしたあと、私が一人で自分の家に向かって歩いていると、初老の男性が私に話しかけてきた。
「君は田中洋一君かな?」
穏やかな口調ではあったものの、私はとっさに身構え、「警察の方ですか?」と聞くと同時に、ゆっくりと左目を閉じた。
「いいや、違うよ」と言う男の周りには赤黒いモヤは見えなかった。しかし、「私は沢木キョウ君の遠い親戚なんだ」と、その男が言ったときには赤黒いモヤが見えた。
「田中洋一君、君が沢木キョウ君の親友だったと人伝に聞いたのでね、少し話をしたいんだ。突然、君のことを訪ねてしまって申し訳ないとは思ったのだが、聞きたいことがいくつかあったんだ。君は田中洋一君・・・だよね。」
「はい、そうですが、何を聞きたいのでしょうか。あの事件のことで自分が知っていることは全て警察に話しました。でも、マスコミの方には話せないことになっているんです。すみません。」と、私は警戒していることを隠すつもりもなく、そう答えた。
「私はマスコミの人間じゃないよ。もちろん、あの事件の謎を追っているわけでもない。だから安心してほしい」と、柔和な表情を顔に浮かべたまま、その初老の男はそう返事をした。
「何が知りたいんでしょうか?」と私が聞くと、「沢木キョウ君のお墓参りに行きたいんだが、せっかくだから彼の好きだった”花”を飾りたいと思ってね。彼の親友であった君なら何か知っているかなと思ったわけだよ」と、その男性は説明をした。
「花・・・ですか?」と私は返事をしたが、私の右目はこのとき、この男が墓参りに行きたいと言っていることはウソだと言っていた。
「本当にお墓参りにいきたいんですか?」と私が聞くと、その男は少し意外そうな表情をして、「今の会話からその質問が出るのは少し不思議ではないかな。田中洋一君、君はそう思わないかね?」と聞いてきた。
私は「そうでもないと思いますけど」と、少しぶっきらぼうにそう答えた。
その初老の男性は、私のそんな態度に気分を害するでもなく、「そんなに警戒しないでも大丈夫だよ。私は君の敵じゃない。どちらかと言えば味方だよ。でも、沢木キョウ君が好きだった花を君が知らないんだったら、それでいいんだ。お邪魔をしてすまなかった。もう君の前には現れないから安心してほしい」と、穏やかな表情のままそう答え、後ろを振り向いた。
立ち去ろうとしている男に向かって私は、「特異な才能」と小さな声で言った。
その言葉を聞いて、その男はすぐにこちらに振り向き直し、驚いた顔をして「君は今、何て言ったのかな?」と聞いてきた。
私が、「『特異な才能』と言ったんです。あなたは、この言葉を待っていたんですよね?」と言うと、その男は、「どうだろう・・・いや、そうかもしれない。うん、私はその言葉を聞きたかったんだと思う」と、最後は独り言のようにそう言った。
そのとき、男の周りには赤黒いモヤは漂ってはいなかった。
「キョウ君、いや沢木君は不思議な力を持っていました。」
「不思議な力、とは?」
「右目のことです。」
「右目?」
「ご存じないんですか?」
「私には君が何のことを言っているのかわからないよ。」
男の周りに赤黒いモヤが漂っているのがはっきりと見えた。
「そうですか・・・。お墓参りのお花のことですけど、沢木君のお墓には、『特異な才能』という花言葉を持つ花が似合うと思います。」
「君はどこまで聞いているのかな、沢木キョウ君から。」
「ほとんど何も聞いていませんし、この右目のことも詳しくは知りません。」
「話しているときに左目を閉じるクセは生まれつきかな?」
「いいえ、沢木君のクセがうつったんです。」
二人の間に沈黙が訪れた。桜の花びらがどこかから、風に舞って飛んできた。
数秒の静寂のあと、「ふぅ」と小さくため息をついて、その男性は私の目を見据えて聞いてきた。
「その右目の秘密を君は詳しく知りたいかい?」
私がその質問にどのように答えたかは、あえて読者の皆さんにお教えする必要はないだろう。なぜなら今、私は『沢木キョウ』と名乗っているのだから。
(SFミステリー小説【永遠の秘密】おわり)