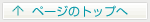失楽 ー夢から覚めた、その先はー
Tweet第3回(更新日:2014年07月08日)
度重なる重圧、身に余る期待
「できて当然」「やって当たり前」
その期待が重かった、あの頃。
辛くて、苦しくて。
一寸先が全く見えなかった、あの頃。
誰かに助けてもらいたくて、
けれども誰を頼っていいのかもわからなかった、あの頃。
一人で突っ走って、ただ我武者羅に頑張って。
「一生懸命やってさえいれば、きっといつかは報われる」
……そう信じて疑わなかったあの頃。
努力だけではやっていけない世界だと、知っているつもりでした。
けれど、いくら頭で理解していても、心で納得できていなければ意味がないのだということを、当時の私は全く分かっていませんでした。
【研究室配属】
帰国後、私は正式に研究室に配属されました。
私のほかに女子が2人と男子が2人。
私を含めて計5人でした。
一研究室あたりの配属人数は0人から5人という規定の中で、上限いっぱいの人数がこの研究室に配属されました。
長らくこの研究室に出入りしていた所為でしょうか。
この時私は、同期ができたというよりは、後輩ができたような気持ちがしました。
配属された男子学生のうちの一人、K君の話をしましょう。
K君もまた私と同じく、教授に青田買いされたひとりでした。
彼は一度T大学(日本の最高学府)を卒業してからこの大学に入学してきていました。
その上、彼が以前やっていた研究と、この研究室の研究テーマが近いこともあり、彼は即戦力として、教授から多大なる期待を寄せられていました。
「今年の学年はイレギュラーが多いね」
研究室の先輩は、口をそろえて言いました。
私はその言葉にさえ、どこか得意げになっていました。
私は育成用の人材として。
K君は即戦力として。
「私はこれから彼と2本柱になって、この研究室を支えていくんだ」
……そんなことを思っていたのです。
事実、教授は正式な配属が下る少し前、私とK君を呼び寄せてこう言っていました。
「今年の新入生は万久里さんとK君だけでいい」
___と。
私は驕っていました。
教授の期待を一身に受けて、自分が然も価値のある人間であるかのように錯覚していたのです。
馬鹿だったのです。どうしようもない、愚か者だったのです。
【配属後】
教授は私たち二人にのみご執心な様子で、他の3人には眼中にない感じでした。
他の3人が、まだ右も左もわからず先輩に付きっ切りで実験を教えてもらっている傍ら、私とK君だけは各自で作業を任されていました。
K君は先輩や先生の期待に違わず、常に優秀なところをアピールしていきました。
一方の私は、熱意があるだけのただの学生に過ぎず、アメリカ帰りという肩書だけが独り歩きしている状態でした。
期待は増す一方。
何とか期待に応えようともがく度に空回りし、小さなミスが目立つようになりました。
研究室での立ち位置が少しずつ、けれども確実に崩れ始め、いつしか私の扱いは、完全にダメなやつに対するそれになり下がりました。
後はもう、悪循環です。
マイナス評価を何とかして挽回しようと、闇雲に頑張り続けても、細かいミスが増えるだけ。
何をやっても責められて、怒られる。
仕舞いには、どうしていいかわからなくなって、途方に暮れていました。
先輩方に頼ろうとしたこともありました。
けれど、それも直ぐにやめてしまいました。
止めざるを得なかったのです。
能力のないくせに教授に可愛がられているのが気に食わなかったのか。
それとも彼ら彼女らは自分の事で手いっぱいだったのか。
……あるいはその両方なのか。
私に対する風当たりは、あまり良いものではありませんでした。
いつしか私は“人に頼る”ということをしなくなりました。
人一倍努力をしたつもりでした。
同期の女の子たちが6時に帰る中、一人日付が変わるまで実験していました。
論文も、浴びるほど読みました。
私に当てがわれた本棚は、一週間もしないうちに論文であふれかえるようになりました。
休みの日も、食事の時間も、寝る時間だって惜しんで努力しました。
けれども、私の評価は下がってゆく一方でした。
……きっと努力の方向性が間違っていたのでしょう。
けれども、その方向性をさえ、指し示してもらえなかった私は、ただ我武者羅に進むほかなかったのです。
目的地も、方向性もわからなくて、どうして正しく進むことができるでしょうか。
心も体も、どちらも限界寸前まで追い詰められていた、その日。
些細なミスをした私を、目敏く見つけた教授は言いました。
「___君は研究を舐めているよね」
「___もう、君に期待してないから」
こんな状況の傍ら、ふと横を見れば、
得意げに話をするK君。
楽しそうに先輩と実験する同期の女の子。
マイペースに実験を進めるY君。(*もう一人の同期の男子)
自分の境遇がみじめでした。
悔しくて、哀しくて、切なくて。
「何で、私ばっかり」
ポツリ、と零れ出た言葉。
何で、何で、何で。どうして、どうして、どうして。
「___どうして私ばっかりこんな目に合わなきゃいけないの」
その日初めて、私は研究室で泣きました。