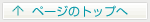失楽 ー夢から覚めた、その先はー
Tweet第2回(更新日:2014年07月01日)
去りし日の、アメリカ
アメリカでの出来事は、今でもうまく言葉にすることができません。
希望にあふれていたあの頃を思い出して、どうしようもなく切ない気持ちになったり。
反対に、無知で浅学な自分の言動を思い出して、恥ずかしさに悶えそうになったり。
酸っぱいような、甘いような、苦いような……
そんな何とも形容しがたい気持ちが、私の心をザワリ、ザワリと苛むのです。
【アメリカ短期留学】
アメリカ留学の条件は、「このラボを第一志望にすること」
それだけでした。
破格の待遇だったと、今でも思います。
この時私は、気軽に研究室を体験させてくれる教授の気さくさや、望めば海外留学をさせてくれる気前の良さに、ひどく感激していました。
なんて、懐の深い人だろう、と。
「そんな懐の深い人の下で、研究ができるなら……」
私はこの研究室を第一志望にすることに、少しも悩みませんでした。
【アメリカでの出来事】
アメリカでの生活は毎日が驚きと感動に満ちていて、毎日が刺激的でした。
平日は研究室に通い、土日は観光を満喫する。
3週間という短い間でしたが、充実した日々でした。
最初は苦労した英会話も、しばらくすると、徐々に自分の意思を伝えられるようになりました。
アメリカ生活もそれなりに慣れてきたころ、ある日本人ポスドクの方に出会いました。
彼の名前を、ここでは仮にJさんと表記することにしましょう。
「やあ、challengerなお嬢さん。アメリカにようこそ!」
その言葉とともに、スッと差し出される右の手。
アメリカナイズされたその姿も、嫌味にならないくらいの好青年がそこに居ました。
「えぇ、君今B3なの!?」
彼は私の年齢を聞くと大げさなくらい驚きました。
「若い、若いね。 でも若いことはよいことだよ。バイタリティもある、熱意もある、体力もある。いいことづくめだ」
彼はここで一度、言葉を切りました。
「ねぇ、君。研究者になりたいんだったら、是非アメリカでPhD(博士号)をとるべきだよ」
考えもしなかった発想に、私は戸惑いました。
一応、「体験」という形で研究室にお邪魔をしていたとはいえ、私はまだ研究室配属前の一学生に過ぎません。
そんな私にとって、Jさんの提案はまさに青天の霹靂、途方もない絵物語のように聞こえました。
戸惑う私に、Jさんは自分がここに来た経緯を話してくれました。
日本で、自分はいわゆる「エリート」であったこと。
彼もそれを自負していたし、周りもそれを認めていたこと。
けれども、どこか物足りなかったこと。
「アメリカに来て、一変したよ」
不思議な表情でした。
悔しさと喜びをないまぜにしたような、そんな顔。
彼は言いました。
「ここにはね、僕が求めてやまなかったものがあるんだよ」
「アメリカに来て、“ものすっごくクレバー”な同僚に出会って自尊心を粉々に打ち砕かれた。」
彼はそう言いました。
滔々と語るその表情からは、いっそ清々しささえ感じられました。
「僕がどんなに考えても……それこそ、一週間や二週間悩み続けても考えつかないようなことを、アイツはほんの瞬きの間に思いつくんだ。
……僕はね、愕然としたよ。
今までどれだけ狭い世界で勝負していたのか、それを思い知らされたね」
あの時の衝撃は忘れられない、と彼は言いました。
「そりゃ、最初はいい気持ちなんて持てなかったさ」
「でも、それってすごいことじゃない?」
自分が努力して、やっと少し追いつけたと思ったら、ひらりと躱されて先を行かれる。
……それは、とても辛いことのように、私には思えました。
まるで「優秀でなければいくら努力したって無駄だ」と。
そう、目の前に突き付けられているような気がするのでは……
私の表情を見て、彼は私が何を言いたいのか、わかったのでしょう。
彼はさらに続けます。
「だって、考えてもみなよ。自分はアイツに勝てない。それを認めるのはつらいことかもしれない。けど、認めてさえすれば。そうすればアイツの存在は、目の前に立ちはだかる、どうしても越えられない壁から、かけがえのない”先生”へと姿を変えるんだ」
いつでも彼の素晴らしい考えを聞くことができる。
いつでも、悩んだときに的確なアドバイスをもらうことができる。
いつでも、自分と同じかそれ以上の視点で、研究について語り合うことができる。
「彼は僕の先生じゃない。ただの同僚だ。だから気軽に、いつでも、何でも聞くことができる。
だけど、彼という存在は僕にとって間違いなく “先生”なんだ」
「君、アメリカにおいでよ」
彼は繰り返しました。
「帰国したら、ラボのPIに相談してみなよ」
「うん、それがいい! きっとPIも喜んで君を送り出してくれるよ。」
その時の私には、彼の提案はとても素敵なものに聞こえました。
きっと私は、酔っていたのです。彼の熱意に、アメリカという非日常に。
気が付けば、
「Yeah, fingers crossed!(そうですね、そうなるといいですね!)」
と笑顔で頷く私の姿がありました。
別れ際、彼は私に一枚の名刺を差し出しました。
「いつか君が、アメリカに戻ってくるときに」
そう言って渡された、シンプルな名刺。
……今では机の奥底に、ひっそりと仕舞ったままになっています。
きっともう、二度と使うことはないソレ。
けれど、捨ててしまうことだけはどうしてもできなくて……
そうしてそれは、時々思い出したように、私の心を逆なでるのです。