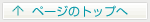Nature/Scienceのニュース記事から
Tweet第99回(2018年2月4日更新)
メモリーT細胞の起源
メモリーT細胞は過去に遭遇した病原体から体を守る働きがあるが、その起源は不明であった。最近発表された2つの研究では、DNAの修飾を経時的に追跡し、メモリーT細胞はエフェクターT細胞から分化することが示された。
・ Akondy et al., Origin and differentiation of human memory CD8 T cells after vaccination. Nature. 2017, 552:362-367.
・ Youngblood et al., Effector CD8 T cells didifferentiate into long-lived memory cells. Nature 552. 2017, 552:404-409.
T細胞は病原体の感染により、ナイーブT細胞からエフェクターT細胞へと増殖・分化して病原体と戦い、感染した細胞を殺す。その後、ほとんどのエフェクターT細胞は死滅するが、病原体の記憶を保持した長寿命メモリーT細胞が残り、再度同じ病原体に遭遇した場合にすぐに対応できるよう備える。このメモリーT細胞は時には10年〜20年といった長期間体内に残っている。ワクチンによる感染症の予防はまさにこのメモリーT細胞の性質を利用したものである。メモリーT細胞が発生する仕組みを解明することにより、ワクチンのデザインを改善することが可能になるのではないかと期待されている。
しかし、メモリーT細胞の起源については、これまでに主に2つの説があった。1つは、感染と戦った後、死滅を免れた一部のエフェクターT細胞がメモリーT細胞へと変化するという説。もう1つは、ナイーブT細胞から、直接メモリーT細胞が分化してくるという説であった。
2017年12月にNature誌に掲載された2報の論文は、CD8陽性T細胞のエピジェネティックなDNA修飾および構造変化といった、核酸配列の変化を伴わない変化を追跡することにより、このメモリーT細胞の起源に迫った。これらのDNAの変化は遺伝子発現と相関していることが多く、まるで本の栞(しおり)のように細胞が遺伝子発現パターンを記憶しておくことを可能にしている。DNAのメチル化はこのような修飾の1種で、メチル化により遺伝子発現は抑制される。
Akondyらの論文では、T細胞のDNAを調べ、ゲノムがきつくパッケージされて転写装置がアクセスできない「閉じた状態」にある領域と、逆に転写が可能な「開いた状態」にある領域を見つけ出した。RNAの分析では、細胞により今まさに転写されている遺伝子群のスナップショットしか得られないのに対し、この著者らが取った方法では、ある転写状態に達するまでの道のりについての知見が得られる。
一方、Youngbloodらの論文では、DNAメチル化を解析することにより、ナイーブT細胞がエフェクター細胞へと分化していくに従い、DNAメチル化パターンが変化することを見出した。ナイーブT細胞においてはメチル化されていた、エフェクター反応を担う重要な遺伝子の多くが、エフェクター細胞においては脱メチル化されていた。著書らは、免疫反応に際して起きるDNAの新規メチル化を担う鍵となる酵素はDNAメチルトランスフェラーゼDnmt3であることを突き止めた。また、メモリーT細胞へと分化していくエフェクターT細胞において、ナイーブT細胞で発現していた遺伝子のメチル化が外れることも発見した。この脱メチル化が、ナイーブ状態で発現していた遺伝子を再度発現させ、長寿命メモリーT細胞を確立維持させるのではないかと考えられる。
ここで重要なのは、メモリーT細胞ではエフェクター分子の発現は低下しているものの、それらをコードしている遺伝子は依然として脱メチル化されたままであるということである。Akondyらはさらに、ワクチン接種のあと、10年もの間生き続けるメモリーT細胞は、病原体に再び遭遇して再度活性化するまでは分裂もしないしエフェクター分子も発現しないにも関わらず、エフェクターT細胞で見られるような「開いたゲノム」のパッケージング状態を示すことも明らかにした。
つまり、エフェクター分子をコードする遺伝子は、メモリーT細胞においてナイーブT細胞よりもエフェクターT細胞における状態に近いということである。このことは、メモリーT細胞が再感染時にすばやくエフェクター分子を発現させることができるという性質と合致する。
以上のように、メモリーT細胞は、いったんエフェクターT細胞の機能に関連する遺伝子を発現した細胞群から分化すること、またメモリーT細胞においては、エフェクター遺伝子の発現はオフの状態にあるものの、自身の分化履歴は保持していることを、両研究は強く示唆している。分化履歴はDNA修飾という形で保持されており、病原体の再感染時にすばやくエフェクターT細胞になることを可能にしている。いわば、エピジェネテティックなDNA修飾が、メモリーT細胞の感染履歴のページに栞としてはさまっており、それにより細胞がエフェクターとしての能力を再度呼び起こすことができるのである。
これらの研究のように、T細胞を異なる細胞群に分けてエピジェネティックな状態を比較することで、細胞系列を調べるのは魅力的な研究ではあるが、それだけではメモリーT細胞がナイーブT細胞のごく一部からも直接分化するという可能性も否定できない。
そこでAkondyらは、分裂しているエフェクターT細胞を重水素で直接標識することで、この疑問に取り組んだ。ワクチン接種後1-2年の間に存在するメモリーT細胞では、重水素の希釈がほとんど起こっておらず、このことは細胞がほとんど分裂してなかったことを示唆している。細胞表面のタンパク質の比較においては、これらのメモリーT細胞はナイーブT細胞に似ていたが、重水素標識により、これらのメモリーT細胞分裂エフェクター細胞から分化したことがわかった。
このことより、ウイルス特異的CD8陽性T細胞は病原体を認識すると大規模に増殖し、エフェクター分子を発現するように自身のDNA修飾を変化させるというモデルが支持される。その後、細胞は分裂をやめ、エフェクター遺伝子の発現を停止し、ナイーブ状態に関連する遺伝子を再度発現させる。
全てのメモリーT細胞が同一なのではなく、一部はナイーブT細胞のように全身を循環し、感染に備えているが、組織常在メモリーT細胞は肺・皮膚・腸管等の病原体が最初に体内に入る経路となる組織に住み着いて、再感染に対する最前線で待機している。これらの多種の異なるメモリーT細胞の起源の解明は今後の課題である。
今回の両研究は、ワクチンデザインの目指すべきところは、メモリーT細胞の起源であるエフェクターT細胞からの強い反応を引き起こすことにあることを示している。しかし、エフェクター細胞がメモリーT細胞になるのを最もよく促進する条件は不明で、その解明は今後の課題となっている。また、Dnmt3などのDNA修飾装置を標的にすることもワクチン改良の有効な戦略となるかもしれない。