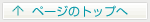研究者の声:オピニオン
Tweet2012年6月21日更新
無題
この文章は私の心の闇を文章化したものである。万人に好まれる読み心地の良い快適な文章ではないことを初めに警告しておく。
私は小さい頃から自分はエリートで歴史に名を残す人物になると思っていた。幼稚園の頃に既に自分は周りとは違うという意識があった。小学校では天才だと色々な人から言われた。有名な中高一貫校を出てT大学に入った。大学院での研究では同期よりも先輩よりもimpact factorの高い雑誌に論文が掲載された。これまでの研究室の歴史の中で自分の論文が一番高いimpact factorだった。しかし、自分だから当然の結果だと思っていた。そのときは、挫折などは凡人が感じるものだと心の底から信じきっていた。
雲行きが怪しくなったのは、某財団から奨学金を獲得して海外に留学してからだった。奨学金も特に苦労せずに獲得できたため、海外のLabで自分が研究すれば2年ほどでCellやNature、Scienceに論文が出るものだと思っていた。しかし、奨学金の期限が終わってもポジらしいデータは出ず、LabのPIからは給料を出せないからLabを出て行ってくれと言われた。
そのとき私は、ポスドク一人の給料も準備できないPIの下だから自分がやっていた研究が上手くいかなかったのだと思った。そんなLabはこちらから辞めてやるとも思った記憶がある。今にして振り返れば、自分の人生で、それが初めて順調に行かなかった期間なのだろうと思う。しかし、失敗ということをしたことがなかった自分には、それが失敗だとは気づけなかった。
次のLabを探しているとき、大学院時代の恩師から某私大の助手(今で言う助教)のポストがあいているとの打診があった。しかし当時は、自分はそんなチャチなところに行くべき人間ではない、と即断をして、その助け舟には乗らなかった。
その後のことは良く覚えていない。というよりも、思い出したくないから無意識のうちに記憶を封印してしまったようだ。いくつかのLabを転々とした。今のLabは4つ目だ。全て職はポスドクである。給料は常に3万ドルから4万ドル。日本円にすれば年収350万円前後だ。長年海外にいるものの、「年収300万円時代〜」や「高学歴ワーキングプア〜」といった書籍が世間を賑わせたのは知っている。まさか自分がその立場になろうとは予想だにしなかった。小さな頃から周りにもてはやされ、T大学で博士まで取ったというのに。
最近、大学院で同じ研究室に進んだ同期が企業から派遣されて同じ街に留学していることを知った。彼は研究がからっきしダメで論文もまともに出せずに修士で企業に行った。正直なところ、どこかで見下していたところがあったと思う。だから卒業後、彼とは何回か年賀状やメールでのやり取りをしただけで一回も会っていなかった。同じ街にいると知っても会おうとは思わなかった。
しかし、何故か彼は家に招待するから夕食でも食べにおいでよと何度もメールをしてきた。非常に丁寧な文面で何回も誘われたので、つい遊びに行ってしまった。OKしたことを今でも後悔している。
当然のことだが彼は結婚していた。子どももいた。幸せを絵に描いたような家庭だった。住んでいる場所も自分のstudioタイプのアパートとは全く異なり、きれいで広かった。しかも家賃はほぼ全て会社がサポートしてくれるとのことだった。
久しぶりに会った彼は学生時代とは別人のようだった。博士号は会社で取ったらしいが、自分が置かれている状況を愚痴りながらも嬉しそうに話していた。いや、嬉しそうというのは間違っている。有り体に言えば、こちらを見下しながら自慢していた。十数年来の復讐のつもりだったのだろう。彼は他にも大学院時代の友人・知人たちがいかに順調に幸せにやっているかを事細かに説明してくれた。内容は詳しくは覚えていない。というよりも、どうやってその場を離れ、自分のアパートに戻ってきたのかも覚えていない。気がついたら、自分の部屋の古くさいベッドの上で大泣きをしていた。涙が止まらなかった。こんなにも自分が泣けるということに驚くほどだった。あんなに泣いたのは何時以来だろうか。小学生のころだろうか。いや、小学生時代は既に周りから神童扱いを受けていたので、あんな風には泣くことはなかったはずだ。ということは幼稚園以来か。
次の日の日曜日は一歩も外に出なかった。ベッドから降りることすら難しかった。動けなかった。食欲もなかったが、何かを食べないといけないと思い冷蔵庫の中を見た。そして、彼の奥さんが作った料理の残りを発見した。綺麗にタッパに詰められていた。どんな会話をしてこれを持って帰ってきたのだろうと思いつつ食べてみた。美味しかった。涙はもう出ないと思っていたのに、なぜかまた涙が出た。脱水症状に陥るのではないだろうかとも思った。
自暴自棄になって・・・と思ったことも何度もある。しかし、今はもう全てを諦めて現状を受け入れた。万年ポスドクでいられたらマシなのだということを受け入れるのは辛かったが、それをしてからは少し気が楽になったような気がする。昔は万年助手(助手は今では助教)という人種をそれこそ虫けらのようにバカにしていた。それなのに、自分がそれ以下で人生を終えるとは不思議なものである。いや、万年ポスドクで人生を終えられたら上出来だろう。上ることはないが落ちることはまだある。落とし穴のある道を目隠しで歩いているようなものだ。
なぜ自分の考えを文章に残そうと思ったのかはわからない。おそらく、この文章がネット上で半永久的に残れば、少しでも自分の生きた証となると考えたのだろう。しかしもちろん本名など出せるはずもない。本名を出し、輝く所属先を示し、上から目線で大勢の前で講演をする姿を何度頭に描いたことか。所詮は夢だったのだ。いやむしろ、夢を見ることこそが人生そのものなのだ。夢を見なくなったら人生は終わり。あとは生命活動がストップするのを待つだけだ。
自分の人生は終わった。世界を変えるような大発見も大活躍も出来なかった。遺伝子も次に引き継げない。しかしそんなものなのかもしれない。学生時代、自分は間違いなくエリートで輝いていた。それで充分だろう。
執筆者:-
もう一つのエリート転落物語