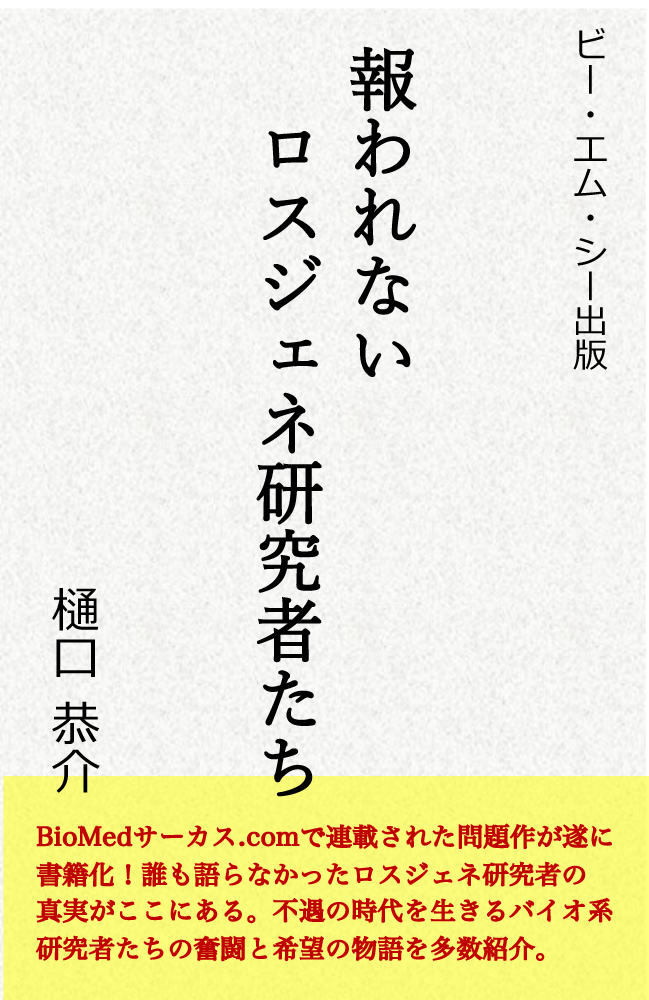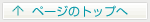研究者の声:オピニオン
Tweet2025年3月30日更新
研究留学のメリット・デメリット〜一世代前との比較
バイオテクノロジーや生命科学の分野にいる研究者には、技術革新と国際競争が加速する中で、多様なキャリアパスが求められています。その中で、研究留学は長い間、バイオ系研究者にとって重要なステップとされてきています。
特に20~30年ほど前は、海外の先進的な研究環境に身を置くことは、若手研究者の夢でありキャリアを飛躍させるための必須条件とさえ見なされていました。しかし、科学技術のグローバル化、インターネットの普及、研究環境の変化に伴い、研究留学がもたらすメリットとデメリットは大きく変容してきています。
本稿では、バイオ系研究者にとっての研究留学のメリット・デメリットを、過去と現在の視点から分析し、その意義を再評価したいと思います。さらに、一世代前の人たちにとってはメリットだったことが今ではデメリットに、またその逆のケースもあるので、それらについても議論を展開していこうと思います。
■ 研究留学のメリット
1. 先端技術へのアクセスとその変遷
研究留学の最大の魅力の一つは、先端技術や最先端の研究設備へのアクセスです。20~30年前の西暦2000年前後、日本のバイオ研究環境は欧米に比べて遅れているとされていました。例えば、次世代シーケンサー(NGS)や質量分析装置のような高額な装置は、一部の国立大学や研究所にしかなく、海外の著名ラボで初めてそれら装置に触れたという研究者が珍しくありませんでした。
この技術格差が、留学を強く後押しした要因の一つともいえます。事実、米国や欧州のラボでは、当時すでにゲノム解析やプロテオミクスが盛んであり、留学経験者は帰国後にその知見を国内に持ち帰り、日本のバイオ研究を牽引する存在となりました。例えば、当時の論文データベースを参照すると、海外留学経験を持つ研究者がNatureやScienceに筆頭著者として名を連ねるケースが目立っていました。
しかし、現代では状況が大きく変わってきています。”技術の民主化”が進み、日本国内でも高性能なシーケンサーや解析ツールが普及しています。クラウドベースのデータ解析プラットフォーム(例:GalaxyやGoogle Cloudの生命科学ツール)の登場により、物理的に海外に行かずとも最先端のデータにアクセスが可能となっています。
2020年代に入ってからの、日本の大学や企業がシングルセルRNAシーケンシングやAIを活用した創薬研究に積極的に投資する姿は、一昔前にあった欧米とのギャップを埋める努力の表れともいえます。とはいえ、それでも海外の一流ラボには独特の優位性が残っています。例えば、CRISPR-Cas9のような遺伝子編集技術の実用化では、技術そのものだけでなく、「どう使いこなすか」という応用ノウハウや実験デザインの哲学は実際にそこに留学してみないと学ぶのが難しいです。これらはマニュアルやオンラインでは伝わりにくく、現場での経験がものを言います。
2. 国際的な人脈形成とコラボレーションの進化
研究留学のもう一つの大きな利点は、国際的な人脈の構築です。数十年前は、海外の研究者と直接会う機会は少なく、学会や留学を通じて築いたコネクションは貴重でした。例えば、筆者の知人で1980年代に米国留学を経験した研究者は、当時同じラボでポスドクをしていた研究者(現在は米国の有名大学で教授)と仲良くなり、帰国後も交流を続けて共同研究をスタートさせました。そして、その共同研究から出された実験結果をもとに、NatureやScienceなどの有名雑誌に論文を発表しています。
このような成功例は、留学がキャリアアップの強力な武器だったことを示しています。人脈は論文執筆だけでなく、研究費申請や国際プロジェクトへの参加にも直結し、研究留学をした研究者の帰国後の研究活動を色々な面で支えることに繋がりました。
もちろん、現代でも人脈の重要性は変わりませんが、日本人以外の研究者との人脈形成方法は多様化しています。ZoomやMicrosoft Teamsといったオンラインツールの普及により、海外の研究者とリアルタイムで議論できる機会が増えました。さらに、XやResearchGateのようなプラットフォームが市民権を得たことで、著名な研究者が最新の知見をそのようなプラットフォームで共有し、彼ら彼女らとカジュアルにコンタクトを取れる時代になっています。今では、バイオ系の国際共同研究がオンラインでの交流から始まったものだと聞いても、特段驚くべきことではないと皆様も感じるのではないでしょうか。
このような環境下では、物理的に現地に行く必要性が薄れつつあります。しかし、それでも対面での交流には独特の深さはあります。例えば、ラボでのコーヒーブレイクや学会後のディナーで交わされる雑談から生まれるアイデアや信頼関係は、オンラインでは再現しにくいです。したがって、人脈形成の手段は増えてはいるものの、留学ならではの「濃密な繋がり」は依然としてある一定の価値はまだあるといえます。
3. 多様な視点と研究スタイルの獲得
海外での研究生活は、異なる文化やアプローチに触れる機会を提供します。1990年代までは、日本のバイオ研究は基礎研究に偏りがちで、応用研究や産学連携は欧米に比べて遅れていました。留学を通じて、米国流の「結果志向」や欧州流の「理論重視」の研究スタイルを学び、視野を広げた研究者は少なくありませんでした。例えば、筆者がある学会で出会った研究者は、ドイツ留学中に学んだシステム生物学のアプローチを日本に持ち帰り、後に国内で新たな研究分野を開拓したと語っていました。このような事例は、留学が日本の研究に新たな風を吹き込んだ証左ともいえます。
もちろん、現在もこのメリットは健在ですが、日本の研究環境自体がグローバル化しているため、国内にいても多様な視点に触れる機会は増えています。海外からの招聘研究者が日本の大学で教鞭をとり、国際的な学会がオンライン開催であるということも珍しくありません。皆様が在籍する大学にも、日本人以外の研究者の数は一昔前よりも格段に増えているのではないでしょうか。
それでも、留学ならではの「異文化にどっぷり浸かる」経験は、研究者としての柔軟性や創造性を育む点で有用です。例えば、アジア出身の研究者が欧米で生活することで、異なる倫理観や研究への姿勢に触れ、帰国後に独自の視点で課題に取り組むケースがあります。この「異文化経験」は、単なる知識の習得を超えた成長を留学経験者にもたらしています。
■ 研究留学のデメリット
1. 時間とコストの増大
研究留学には、今も昔も多大な時間とコストが必要となります。20~30年前は、これは「投資」と見なされ、将来のリターンに期待が寄せられていました。博士課程やポスドクの時期に2〜5年間海外で過ごすことはキャリアのステップアップとして当然視され、奨学金(例えば日本学術振興会の海外特別研究員制度)や研究費も比較的潤沢でした。
対照的に、現代ではこの負担がデメリットとして際立っています。日本の研究予算は削減傾向にあり、若手研究者の経済的余裕は限られています。今や、生命科学の分野でも、博士課程修了者の少なくない割合が非正規雇用に就いており、留学資金を捻出する余裕はおろか、日々の生活に苦労する人も珍しくありません。さらに、海外での生活費は高騰し、特に米国や欧州の大都市では家賃や保険費用が研究者給与を圧迫しています。例えば、ボストンやサンフランシスコでは1ヶ月の家賃が3000ドルを超えることも珍しくなく、家族を帯同すればさらに負担が増します。
また、研究のスピードが加速する現代では、数年間のブランクがキャリアに致命的な遅れをもたらすリスクもあります。留学中に国内でのポジションを失い、帰国後に就職難に直面するケースも報告されており、時間とコストのリスクは以前よりもずっと顕著です。
2. 家族や生活への影響とメンタルヘルス
1980年代および1990年代は、研究留学に帯同する配偶者は”主婦”をして”夫”の研究留学を支えることが普通でした。そのため研究に専念する環境は整っており、さらに帰国後の安定したポジションも期待できたため、留学中の生活面における多少の不便さは許容されていました。
しかし、現代では研究者のライフスタイルが多様化し、配偶者の仕事のキャリアも重視されるようになっています。そのため、単身で留学をして長期の別居を強いられ、家族関係に亀裂が入るケースもあります。また、家族を帯同する場合でも、配偶者に負担を強いることとなり家族間の問題が生じるリスクがあります。さらに、配偶者の就労ビザや子どもの教育環境も問題です。例えば、配偶者の就労が制限されるビザが多く、配偶者が現地で働くことは容易ではなかったりします。
これらストレスは、メンタルヘルスにも影響を及ぼします。特に日本人男性の場合は、異文化適応や孤立感について対応するのが難しい人が一定数の割合でいます。それでも一昔前は「我慢してでも得るものがある」とされていたので”我慢”できていましたが、現代ではそのようなメリットが少なくなり、またメンタルヘルスへの関心も高まったことから、一部では、生活の質を犠牲にする留学の価値そのものが問われ始めています。
3. 帰国後のキャリアリスクと市場の変化
かつて、海外留学は「箔付け」としても機能し、帰国後の大学教員や企業研究者への道を開いていました。2000年代初頭までは、海外経験を持つ研究者が優先的にアカデミック・ポジションに採用され、教授職に就くケースが多く見られました。しかし現在では、国内の研究職市場が縮小し、ポスドク過剰問題が深刻化しています。文科省のデータによると、2020年代のポスドク数は約1万5000人に対し、正規雇用のポジションは年間1000件程度しかありません。この競争環境では、留学経験が必ずしも評価されず、「海外での成果を国内で活かせない」ケースも増えてきています。
特にバイオ分野では、企業との連携が重視される中、留学中に産業界との接点を築けなかった研究者は不利になりがちです。例えば、製薬企業が求める実践的なスキル(例:臨床試験のデザインや規制対応)を海外の基礎研究ラボで習得するのは難しく、国内での製薬企業との共同研究経験の方が評価されることもあります。一昔前はメリットだった「国際経験」が、今では「国内でのコネ不足」や「研究トレンドからの乖離」といったデメリットに転じるリスクを孕む結果になってしまっています。
■ 結論:研究留学の未来と柔軟な選択
バイオ系研究者にとって、研究留学は依然として魅力的な選択肢ではあります。しかし、一昔前のような「必須条件」ではなくなり、個々の目標や状況に応じた「オプション」へと変化しました。メリットを最大化しデメリットを最小化するには、明確な目的意識と計画性が不可欠です。例えば、特定の技術習得やコラボレーションを目的に1〜2年の短期留学を選ぶ、あるいはオンラインでの国際交流を補完的に活用するなど、柔軟なアプローチが有効だと思われます。
科学のグローバル化が進む中、研究留学の意義は「場所」から「経験」へとシフトしています。バイオ分野の未来を担う研究者にとって、留学は単なるキャリアのステップではなく、自己成長と世界への貢献を両立させる手段となるべきなのかもしれません。以前の成功モデルに囚われず、現代の環境に適した形で留学を再定義することが求められていて、研究留学をするしないの正解は、結局のところ、研究者自身が決めることなのかもしれません。
著者:山岡あかね(サイエンス・コミュニケーター)