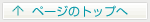失楽 ー夢から覚めた、その先はー
Tweet第5回(更新日:2014年07月22日)
幸せな日々、そして終焉。
【共同研究】
R先輩が来てからというもの、私はまた、夜遅くまで実験をするようになりました。
互いの結果を見せ合い、ああでもない、こうでもないと話し合うのは本当に楽しいひと時でした。
誰かと実験の話を共有し合えるということが、嬉しくて仕方ありませんでした。
お互い、共同研究なんてしたことがなくて、いつも自分一人で実験していたからこそ、余計に互いの存在の有難さが、身に染みていました。
「こういう実験もしたい」「あの現象をはっきりさせたい」
話題は尽きず、いつも夜遅くまで話し込んでいました。
研究の話をしたのは何も研究室の中だけではありません。
二人で遊びに行った時も気が付けば実験の話をしていました。
カラオケに行ったはずが、歌も歌わず実験の事について話し合っていたり。
一緒に食事に行った際、日常生活の話をしていたはずが、いつの間にか研究の話になっていたり。
「嫌よ嫌よも好きのうち」
「結局、なんだかんだ言っても、私たちは実験が好きなのよ」
そう言っては二人で笑い合っていました。
...けれど。
幸せな時は長く続かない、とはよく言ったもので。
終わりの時はひたり、ひたりとすぐそこまで迫ってきているのでした。
【迫りくる影】
「君たちはこの実験で何が見たいの」
「こんな曖昧な系じゃ、実験しても意味ないよ」
「君たちのテーマがいま世界的にどこまで明らかになっていて、どこからが君たちのオリジナリティなのか、はっきりさせないと」
「...ねぇ、君たちいったい何がしたいの? 何にも見えてこないんだけど」
「...」
何も、答えられませんでした。
左遷されてから初めての、セミナーでの実験報告の日、私たちの研究は散々な指摘を受けました。
(*“共同研究”という名目上、左遷されても本部のセミナーだけは参加義務があります)
きっと、経験豊富な研究者なら、答えられて当然の質問だったのかもしれません。
ですが私たちは、片や研究室に入って半年の、片や一年半の、未熟な研究生でしかありません。
指導教官に教えを乞いながらでしか、実験を進められない私たちに、一体何を望むというのでしょうか。
今の実験系だって、私たちが自分で考えたものではなくて、共同研究先の指導教官が設定してくださったものでした。
「そんなこと、私たちに言われても」
「私たちじゃなく、私たちの指導教官に言ってよ」
自分たちの無知と認識の甘さを恥じながらも、これが私たちの偽らざる本心でした。
共同研究先の研究室に戻り、本部のセミナーでのことを指導教官に報告するも、
彼は「ふーん」の一言。
実験系を変えた方がいいのでは、と進言すれば逆に責められました。
挙句、
「あいつらは何もわかっていないんだから、あいつらの言うことは無視しておけばいい」
などと言い出す始末。
私たちは指導教官に対して不信感を抱き始めるようになりました。
【実験中止】
こんな状態で、研究がうまくいくはずもありません。
先輩と一念発起してから、わずか数か月。私たちの研究は頓挫しました。
よくあることです。教授の気分次第で、実験が中止になることなんて。
テーマや実験系の設定が曖昧すぎることもあり、
呆気ないほど簡単に、私たちの共同研究は幕を閉じました。
ちょうどそのころ、本部では新しい指導教官を迎え、新しい研究が始まろうとしていました。
R先輩はそのチームの一員に抜擢され、本部へと戻ることになりました。
本部に戻ることが決まった時、彼女はとても残念そうにしていました。
「万久里と実験できなくなるなんて、哀しい」
「せっかくここまでやってきたのに。まだ、私たちは何も成し遂げていないのに」
「...万久里も一緒に帰れないの? 」
私は、彼女が別れを惜しんでくれた、その事だけで、もう十分でした。
「彼女まで、こんなところに落ちてほしくない。ここにいるのは私だけで十分」
日ごろから、常々そう思っていた私は、彼女の本部帰還の話を聞いたとき、寂寥感よりもむしろ安心感の方が勝りました。
あぁ、私は彼女を巻き込まなくてすんだのだ、と。
もともと力のある人だったのです。こんなところで燻っていていい人材ではなかったのです。
私は彼女の本部帰還の話に、心から安堵しました。
***
...十分だったはずです。
“哀しい”と“寂しい”と...そう言ってくれただけで、満足していたはずでした。
私は、彼女と実験をするうちに、いつしか夢物語に囚われていたのかもしれません。
“万久里、ダブルファーストで論文を出そう!”
...もしかしたらこの夢が、現実になるのではないか、と。
いつしか本気でそう思っている自分がいました。
もっと一緒に研究がしたかった。
二人の努力を、論文という形で世の中に送り出したかった。
論文にすることは無理でも、せめて二人が納得のいく形で研究を終わらせたかった。
夢物語だと、わかっていたはずなのに。
いつの間にか本当に叶いそうな、そんな気さえしていたのです。
数日後、出欠表から彼女のネームプレートが消えていました。
こうして私はまた、ひとりぼっちになりました。